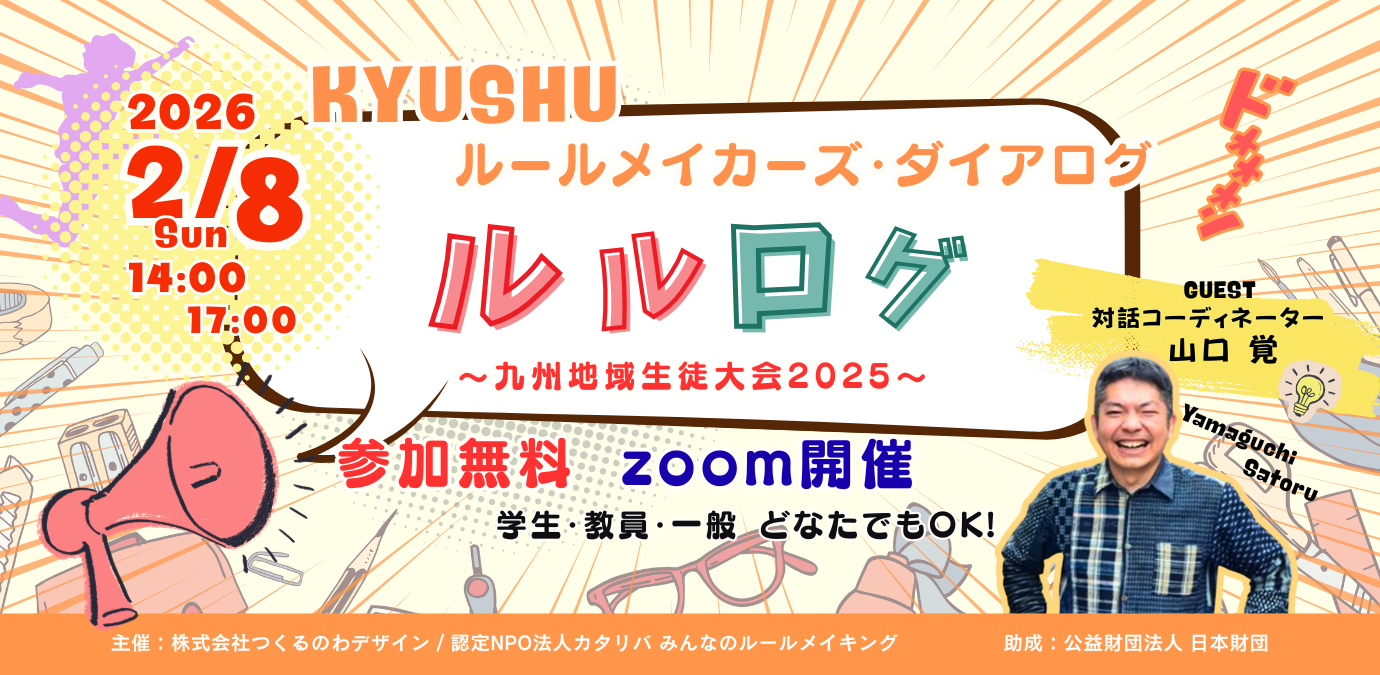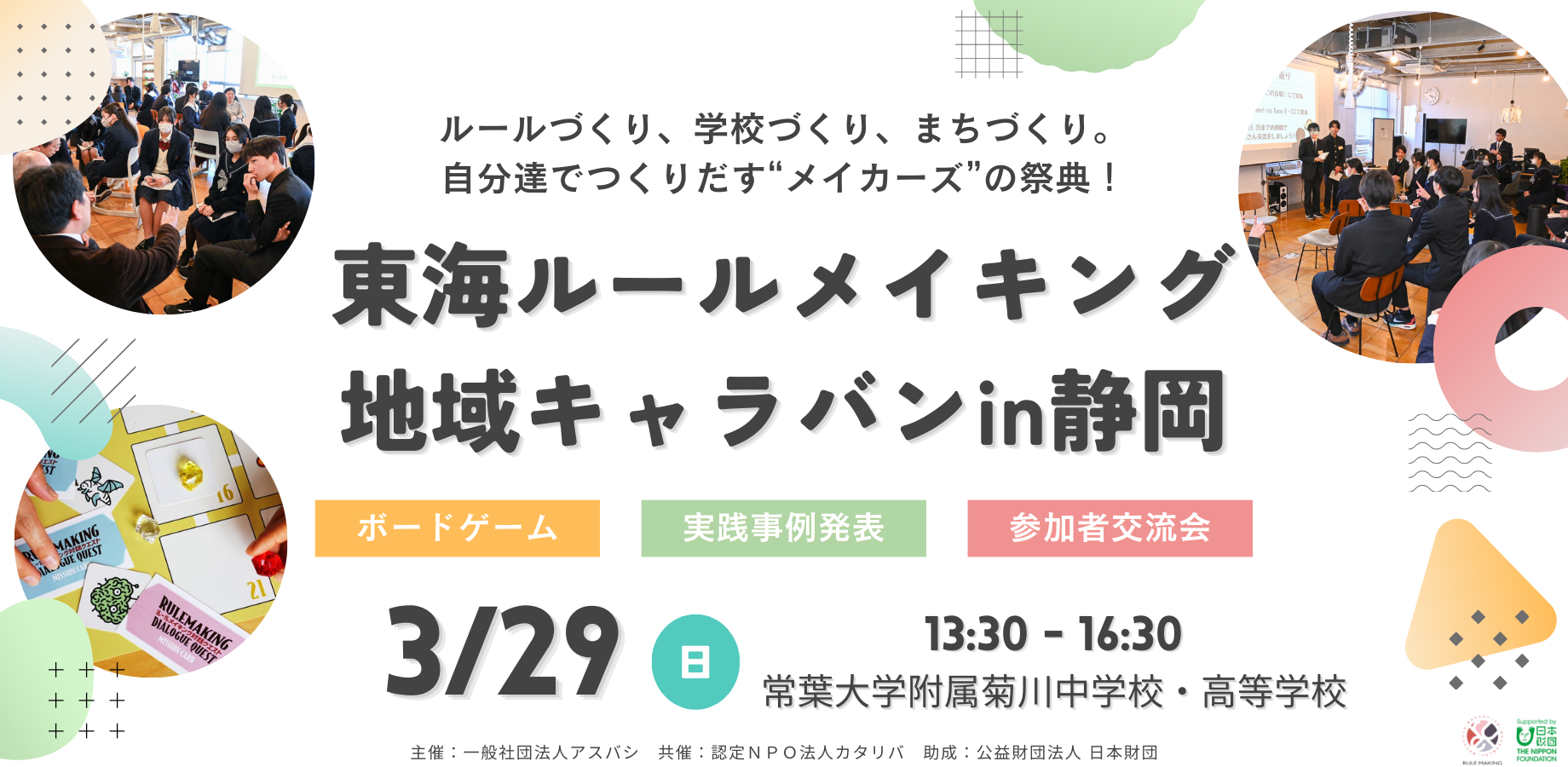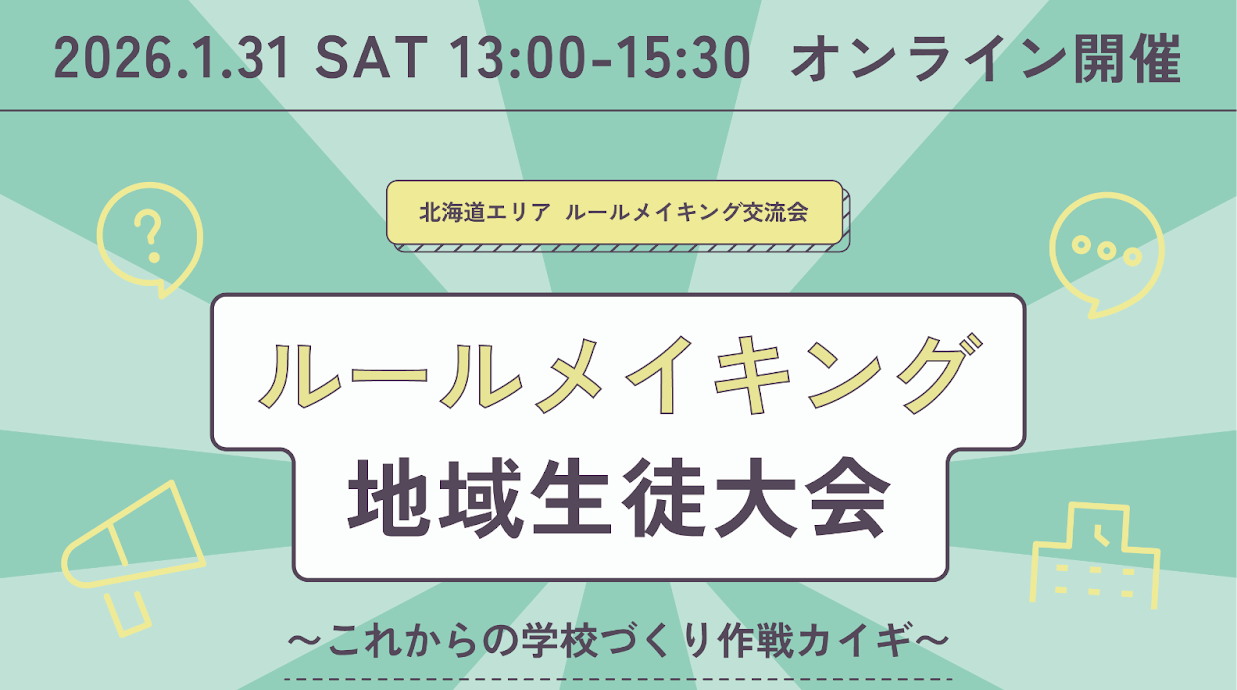
- インタビュー
- 校則の見直しは学校としての「チャレンジ」ーお互いの価値観を伝え合う機会に
校則の見直しは学校としての「チャレンジ」ーお互いの価値観を伝え合う機会に
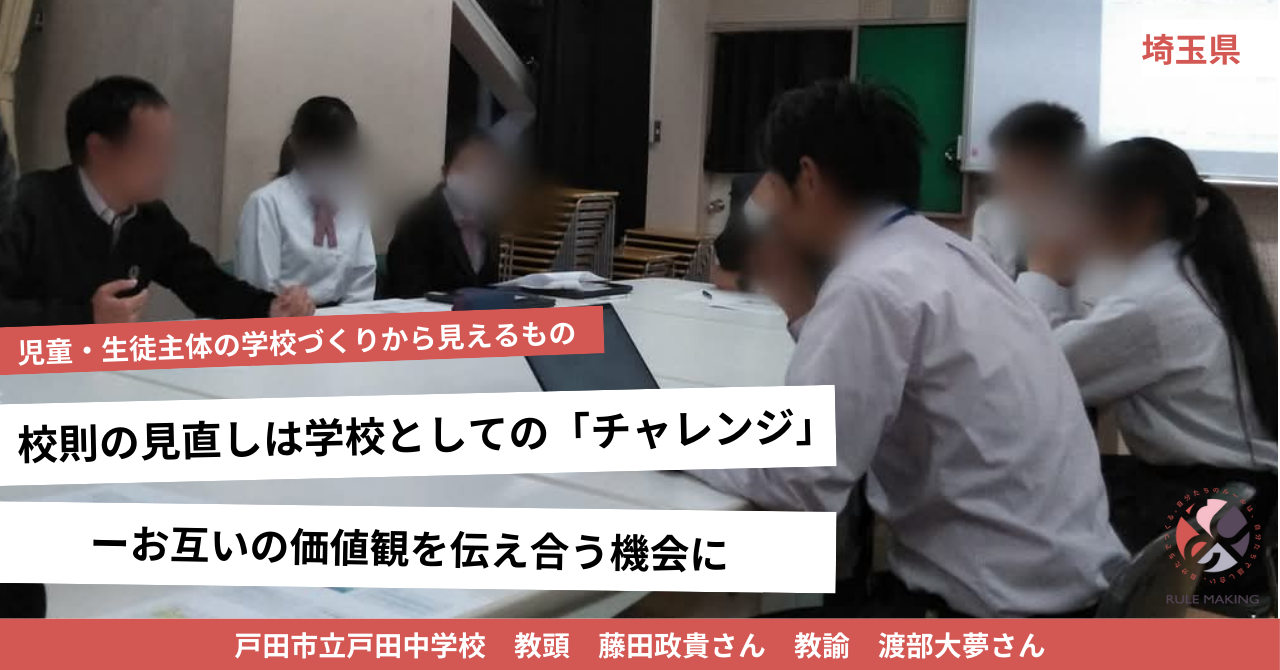
対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は480校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。
連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。
埼玉県戸田市立戸田中学校では決められた校則だけではなく、教員間だけで共有される「指導のポイント」という資料があり、指導をめぐって学校と家庭の認識にズレが生じていたといいます。校則の見直しを学校としての「チャレンジ」と捉え、お互いの価値観を否定し合う摩擦ではなく、価値観を伝え合う機会をつくっていくことを目指しています。活動を中心なって支えてきた教頭の藤田政貴さん(以下、藤田)と教員の渡部大夢さん(以下、渡部)にお話を伺いました。

埼玉県戸田市立戸田中学校 教頭
藤田 政貴
埼玉県戸田市教育委員会・生徒指導主事等を経て、2022年度に戸田市立戸田中学校に着任。学校は「人である」という考えを大切に、教員や生徒が何でもトライアルできる環境づくりに取り組む。

埼玉県戸田市立戸田中学校 教諭
渡部 大夢
2020年度に戸田市立戸田中学校に着任。2024年度より生徒指導主任となり、校則の見直しに向けて全校生徒や教員にアンケートを実施するなど、中心となって活動している。
ーー2024年度から校則の見直しに取り組んでこられたようですが、きっかけは何だったのでしょうか。
渡部:私は昨年度から教員でつくられる生徒指導委員会に所属していました。校則見直し活動は2023年度にも取り組んでいましたが、当時は何かが大きく変わるということはありませんでした。
私は本校に来て5年目になるのですが、生徒や保護者から「何でこの校則あるのですか?」という問い合わせを受けることが多かったです。ただ、自分の中で納得できるような回答を返せていないことがほとんどでした。例えば、髪型でいうとツーブロックがだめな理由は曖昧ですよね。そこで、校長や教頭の指導のもと、本格的な校則の見直しを始めました。
本校はとにかく校則が細かいです。今回は、髪型、靴下の色、冬のセーター着用の仕方の他、現在は体育館履きと上履きの2セットを用意していますが、一体型の靴になるため1セットでよいといった、4つの校則を変えることになります。
まず教員側に校則検討委員会の設置を提案し、「今の学校生活の中で気になるところやこうした方がもっと良くなるのではないか?」といった視点で、全校生徒向けにアンケートを実施しました。回答で最も多かったのが髪型と靴下に対する意見だったので、この2つをメインに考えました。他にも教員にも同様のアンケートをとってみると、同様に髪型と靴下に関する意見が多く、同じ項目でも生徒と価値観のズレが生じていることに気づかされました。

例えば、「女子生徒は耳より下で髪を結ぶ」という表記は、実際の生徒手帳には一切ありません。
一方、教員の「指導のポイント」という別の資料に、上記のような表記があり、大混乱を招いている状態でした。ツーブロックも同じで、生徒手帳には「特異な髪型にはしない」という表記だけですが、「指導のポイント」では禁止されています。この資料は私が着任した時からあり、生徒と保護者には公表されていないので、それが、教員と生徒の間で価値観のズレを生じさせる原因になっていました。
ーー校則の見直し活動を始めるにあたって、教員側からどの様な意見がありましたか。
藤田:ほぼ全員の教員の中に、教員側だけの基準があり、それがきちんと生徒や保護者に共有されていないという違和感があったのだと思います。でも、今までは教員側の上から締め付けるような、いわゆる高圧的な指導が成り立ってしまっており、生徒も保護者もそこに違和感を持たなかったのかもしれません。時代の流れは変わってきており、ツーブロックはすでに特異な髪型ではないですが、学校のルールが多く、整備が追いついていなかったのだと思います。
ーー実際には、見直しに向けてどのように動いていらっしゃるのでしょうか。
渡部:Googleフォームで全校生徒にアンケートをとりました。また、毎年5月に生徒総会が開かれるので、そのタイミングで「学校を良くするために何が変えられるのか」というテーマで、各学級で話し合ってもらいましたね。
藤田:我々としては2023年度から「校則を変えていく」という意識があり、その時にも生徒に校則に関するアンケートをとっています。当初は、生徒から髪型などの意見が出てくると予想していたら、実際にはあまり意見は出てきませんでした。「 髪型をああしたい、こうしたい」というより、「緩めてくれるのなら学校がやってください」というような、他人事の回答でした。大半の生徒たちが「別に今の校則でも不自由はない」「多少我慢すれば問題ない」といった考えで、おそらく変える労力と比べたら、変えなくてもいいのではないかと思っていたのかもしれません。
ですので、今年度は渡部さんが質問の仕方を一工夫してくれました。アンケートで例えば「校則を見直した時にどう思いますか」という問いにしたら、「髪型って本当に学校生活に影響があるのですか?」「私はこういう習い事をしているので、こういった髪型がよい」といった回答が出てくるようになりました。単純に「学校を良くするためにどうしたらいいでしょうか?」という聞き方にしたのです。そうしたら、生徒たちの意見が急に出やすくなり、驚きましたね。聞き方1つで全部変わるのだと実感しました。
渡部:このアンケートを基に教員や生徒指導部の中で校則について考えた方が早いですし、いちばん楽です。ただ、学校で過ごすのは生徒であり、それを受け入れてくれる保護者の方にも様々な意見がある。教員だけで押さえつけるような進め方は、私の感覚的にもう時代に合わないのでは?と思っています。
ーー校則を見直していくことに、地域の方や保護者の方から不安の声などは聞かれなかったでしょうか。
渡部:そういった声はなかったですが、校則を変えてほしい生徒とそう思っていない生徒がいるので、どちらか一方の生徒が過ごしにくくならないか不安なところはあります。
藤田:ルールを変えることへの受け止め方は人それぞれですよね。生徒会代表、保護者代表に集まってもらい開かれた校則検討委員会では、髪型の新校則のたたき台として案を出しています。そこでは、モヒカンなどの具体的な髪型の写真を入れて「これはだめですよ」と示していました。

今度はそれを学校運営協議会で示したら、地域の代表の方から「昔に戻っちゃったね」という言葉がありました。確かに 80年代・90年代の校則って ガチガチだったんですよね。私が子どもの頃は「 パンチパーマ禁止」などと様々な禁止事項が書いてありました。その時、「戸田中生らしさをもっと大事にしてほしい。地域の宝である子どもたちで、 どういう姿が戸田中生らしさなんだろうということをぜひ学校でも考えてほしいです」というアドバイスをいただきました。

もう一度生徒指導委員会に持ち帰り、結果的に具体的な言葉は削除しました。その代わり に、「戸田中生らしい髪型を各ご家庭でも考えていただきたい。何かあった時には私たちも声かけしますのでよろしくお願いいたします」というような記述にしました。つまり、まずはご家庭でも戸田中生らしさを考えてもらい、何か気になることがあったときに「こうしよう、ああしよう」とご家庭と学校で対話していくことが大切だと気づかされました。
4月から新しい校則になり何か起こるかもしれないですが、それはお互いの価値観を否定し合う摩擦ではなくて、伝え合う機会として捉えています。 これは本校としてのチャレンジですね。
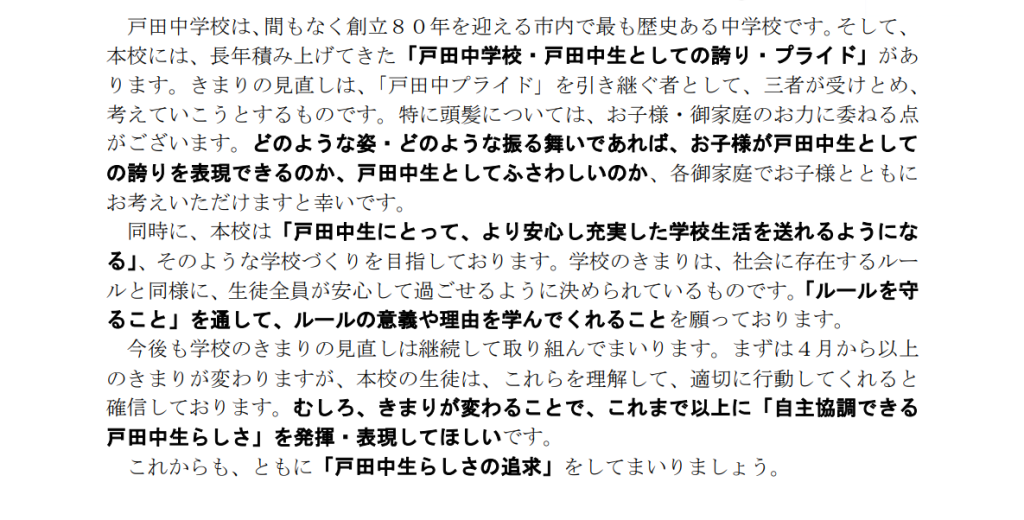
ーー私たちも「対話」のプロセスは非常に大切だと思っています。一方で、よりよい対話の場を目指すために、どのような工夫をされていますか。
藤田:最初にお伝えした「指導のポイント」という内部資料の基準が隠されていたことで、トラブルが発生しました。逆を考えると、我々がオープンになれば、保護者や生徒たちもオープンになれる。そこは、人間と人間の情の部分が大きいのかなと思っています。
教員の中では、やはり管理職側が「何かあったら出て行くよ」と、他の教員を守る後ろ盾がないとやりづらいと思います。管理職の責任としてできることはするので、その分教員には思いっきりやってほしいですね。
学校とは、結局「人」だと思っています。本校は生徒たちがとても生き生きしています。それは学校にいる教員ら「人」が元気だからではないでしょうか。それが、生徒を人として育てる環境作りにも繋がっているので、私は基本的に生徒たちにも教員にも「思いっきりやってください。責任はこちらが取ります」 というスタンスです。トライアル自体をどんどん奨励して、小さいエラーを早めに修正していくことを心がけています。
ーー校則の見直し活動を通して、指導観などが変わった部分はありますか。
渡部:私自身 最初の2年間は特別支援学級の担任をやっていました。通常級の教員や生徒をちょっと離れた位置から見ることも多く、学校生活のきまりなどに違和感を持つものがいくつかありました。例えば特別支援教育の観点では、生徒個人のそれぞれの特性や個性をとても大事にします。それを踏まえて通常級を見た時に、「髪型も個性だし、特性でもあるから幅を広げてもいいのではないか」と思っていました。でもルールがあることでみんなが快適に過ごせるなどの側面もありますよね。ですので、生徒や保護者の意見をしっかりと聞いていく必要があると思えるようになりました。
ーー校則見直しの活動を通して、生徒に見つけてほしい力はどんなものでしょうか。
渡部:何でも変えていくことではなく、守らなきゃいけないものも大切にしながら、校則は何のために存在するのかを考えることを大切にしたいと思っています。進学した高校や社会の中で、居心地のいい場所を作るのは自分、悪くするのも自分。それを考えられるような生徒になってほしいです。
藤田:新年度の4月から我々がやらなくてはいけないことはルールマネジメントではないでしょうか。こちらのほうが重要であり、どうやって校則見直しの流れを継続していくかを考えています。 「ルールを変えた」だけでなく、ルールを通してどのようにみんながよりよい学校生活にしていくか、もっと生徒から意見が出てくるとよいなと思っています。それを吸い上げて、教員やPTAなど様々な立場の方と対話を深めていきたいですね。「ルールメイキング=校則を緩める」ではなく、「みんなにとっていいものを考えよう」という感覚は絶対忘れずに取り組みたいと思っています。みんなのためのルールを、みんなで守り、みんなで結び直していくプロセスを大切にしたいですね。
「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?
ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。
登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。
新着記事
カタリバではルールメイキングに取り組む
学校・先生・自治体をサポートしています
すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。
まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。