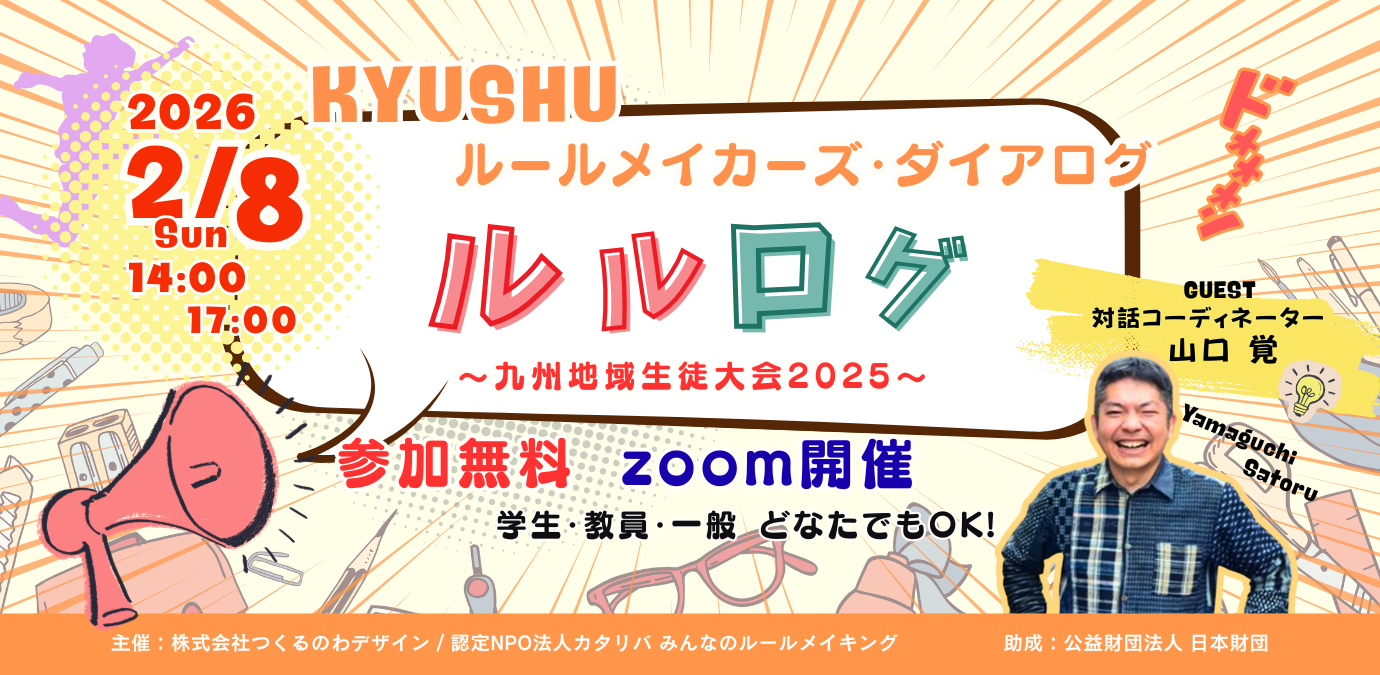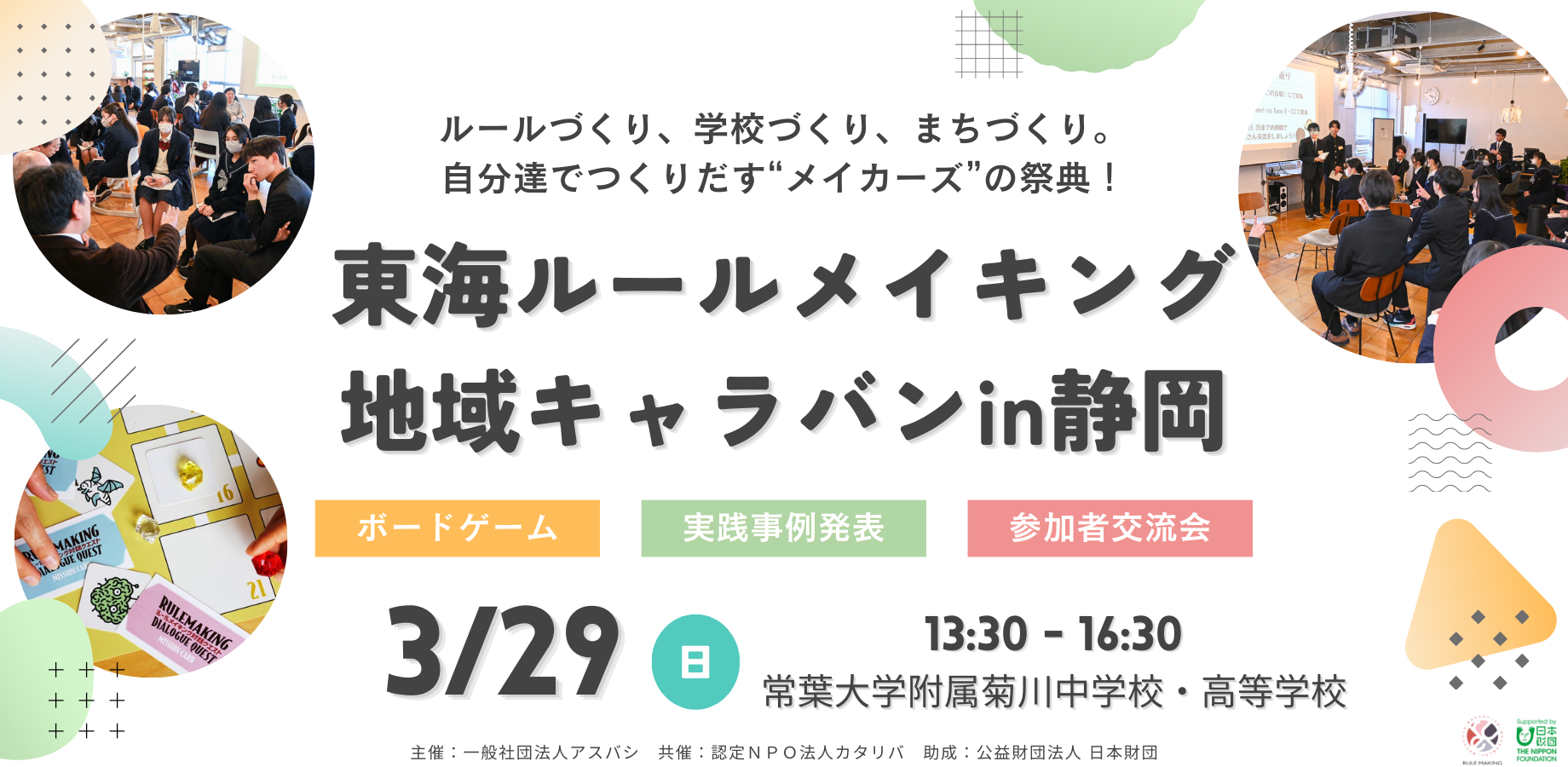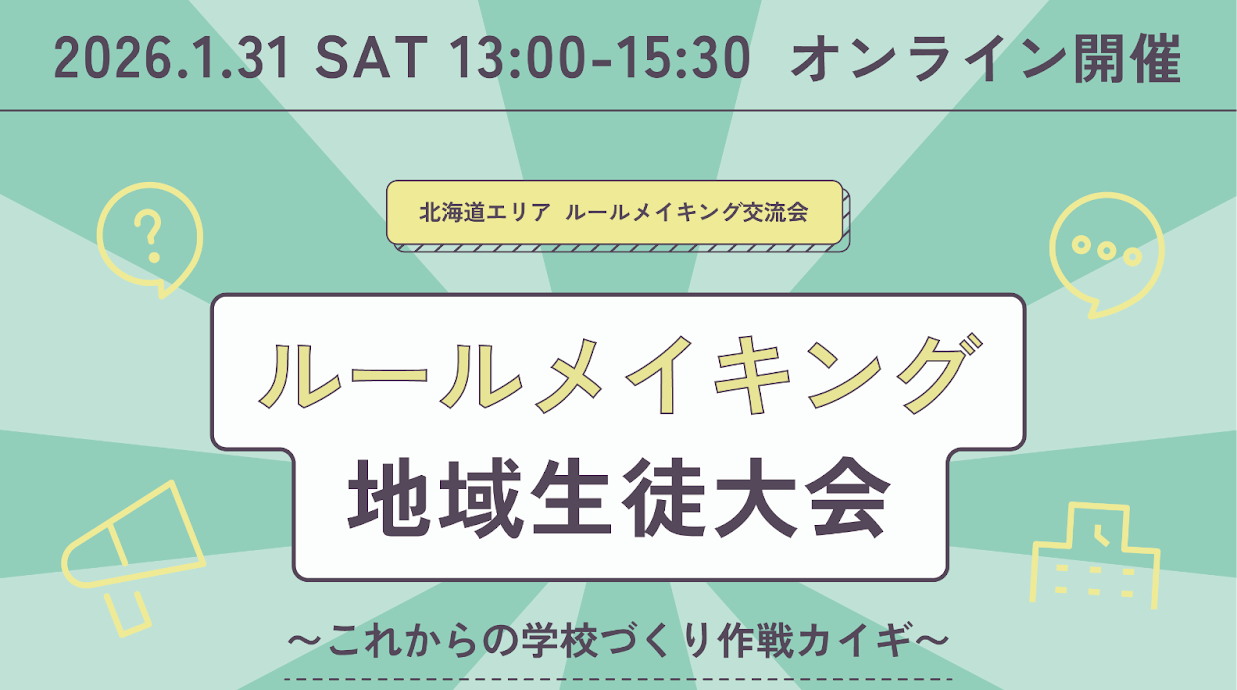
- インタビュー
- 株式会社ZOZOが目指す「カッコよく、笑顔でいられる」世界とルールメイキングの共通点とは
株式会社ZOZOが目指す「カッコよく、笑顔でいられる」世界とルールメイキングの共通点とは
インタビュー
企業事例

校則を題材に、対話を通して納得解をつくるプロセスで学びを深める「みんなのルールメイキング」。取り組みは学校現場だけにとどまらず、企業による参画も徐々に広がってきています。国内最大級のファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZO(千葉市、以下ZOZO)。全国の学校で出前授業を行うほか、昨年のルールメイキング・サミット2024に企業ボランティアとして参加し、社員が中高生のファシリテーターを担うなど、ルールメイキングとの連携も実現しています。
今回は、ZOZO・CI本部フレンドシップマネージメント部CSRブロックの篠田ますみさん、鹿子聡美さん、李銀珠さんにインタビューにご協力いただき、アパレル事業だけでなく、次世代へのサポートも「本業」として力を入れる理由をお聞きしました。
企業理念に直結する「本業」としてのCSR活動
ーールールメイキングの記事にご登場いただくのは、高校生のインタビューにご対応いただいた2024年以来となります。今回は改めて、ZOZOさんがルールメイキングとの協働を含む教育事業を展開するようになった経緯をお聞きします。
篠田ますみ(以下・篠田):ZOZOでは、2021年からサステナブルステートメント「ファッションでつなぐ、サステナブルな未来へ。」を掲げ、FUTURE FOR YOUをコンセプトに、「教育」「スポーツ・文化」「寄付・支援」の3分野で社会貢献活動を展開しています。ZOZOの企業理念は「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」であり、10年後も100年後も、世界中がカッコよく、笑顔でいられるために、未来を担う次世代を応援しています。
鹿子聡美(以下・鹿子):教育分野では、小学校から大学まで、キャリア教育を中心に出前授業を行っています。ほかにも探究学習の支援や職場体験の受け入れ、教員研修も実施していますね。出前授業は2020年に取り組みを開始して、2024年度は約140校に出向いて実施するほどになりました。

ーーカタリバも学校現場の支援を行いますが、1年で140校はものすごい数字です。
鹿子:出前授業を始めて2年目からは千葉県内の市役所に電話して出前授業パンフレットを学校に配布していただくなど、より多くの学校で実施させていただけるよう手探りで試行錯誤している状態でした。少しずつ活動が広がり、今では毎日さまざまな学校を飛び回っているような状況になりました。
教育以外の社会貢献活動も多岐にわたります。スポーツ分野では、ネーミングライツやユニフォームデザインなどを通して、子どもたちの夢や未来を応援しています。寄付・支援としては、行政やNPOへの寄付だけではなく、児童養護施設の夏祭りに社員が参加して一緒にヨーヨー釣りをしたり、ZOZO社内の野球部と子どもたちが野球の試合をしたりするなど、現場での活動もあります。野球はあっさり負けてしまいました(笑)。
ーー企業のCSR部の形は多種多様ですが、ZOZOフレンドシップマネージメント部の活動は、自ら現場で活動を作り、その熱量は際立って高いように感じます。
李銀珠(以下・李):本業は別にあって兼任としてCSR活動をやっていると思われることも多いのですが、私たちはこれを専任として実施していますし、2030年までに100万人の子ども・若者とつながり支援するという具体的なKPIも設定しています。活動を通してZOZOを知っていただくことや、ファンになっていただくことで世界中を笑顔にする仲間を増やしていくことが理念の達成につながるという考えですが、何よりも活動を通して出会った次世代の皆さん自身が、ZOZOから聞いた話が参考になったり、ポジティブに人生を過ごすためのヒントになったら、という思いがあります。
篠田:2020年から出前授業を始めるにあたっては、「理念達成の未来のために、やらない理由はない」と会社に実施の提案をしました。上長も共感して背中を押してくれましたし、ZOZOには社員自身の挑戦を後押しする風土があることも大きかったと思います。
教育事業だけでなく社内でも自主性を尊重
ーーそんな中、カタリバとの接点は2022年、初めは寄付を頂く形でスタートしました。
篠田:社会貢献活動の一環でゴルフ大会を実施した際に、売上の一部を寄付するための寄付先を探していたんです。すると、カタリバのルールメイキングや居場所づくりの取り組みが、ZOZOの目指す未来像と親和性が高いことが分かりました。「くすぶっているけれども、どう放出したらいいかわからない」というエネルギーを抱えた若者に伴走することや、未来を自分で決定して作り出していくことにとても共感したので、「この団体となら良い取り組みができそう」と寄付させていただくことに決めました。
鹿子:自分で考えて行動し、社会を動かしていく力を育んでいくというのは(ZOZOとカタリバの)共通のビジョンでした。そこから、2022年にはオンラインイベントもやりましたよね。
篠田:「寄付だけでなく、一緒にできることを探したい」とカタリバさんともお話していたんですよね。寄付は会社の経営状況の影響を受けますし、実際の活動をご一緒することで私たちの学びにもなりますから。このイベントでは、社内でオリジナルの時短勤務制度を新設したときのことを、企業におけるルールメイキング的な取り組みの事例としてお話しました。
鹿子:普段の出前授業では、どうしてもこちらからの「伝達」になってしまう部分がありますが、このイベントでは対話的な時間を取れたのが印象的です。ルールメイキングに取り組む生徒さんたちと一緒に、「違う立場の人とどうやって話をしていく?」などについて考えました。

ーーその後2023年に、李さんがチームに加わられたんですよね。
李:はい、2023年10月に、ブランド営業部から異動しました。正直に言うと、社内にこうした活動があることをあまり知らなかったのですが、社内公募(部署異動制度)の、出前授業運営スタッフの募集を見て、「これだ!」と手を挙げることにしたんです。
私は洋服が大好きでZOZOに入ったんですが、もともと保育士志望で子どもに関わる仕事もしたいなと思っていたんです。「このチャンスを逃したら、ZOZOで子どもに関われる機会はもう無いかもしれない」と思いましたね。
鹿子:実は私もスクールカウンセラーを志していたことがあって、社内公募に手を挙げてチームに加わったんですよ。2020年だったので、まだ篠田さんがほとんど一人ですべてをやっている時期でした。それまで私は物流部門で商品管理などを担当していたので、最初は別会社に転職したくらい、やっていることが違うなと思いました。
李:コロナ禍でリモート勤務に慣れていたので、毎日学校現場に足を運ぶ生活に本当に驚きました(笑)。
篠田:自分の意志で集まったメンバーだからこそ、会社にやらされるのではなく自分たちで意義を考えながら事業を拡大してこられたんだと感じますね。
民間企業の立場で教育現場に価値を
ーー2024年秋には、ルールメイキング・サミット2024でファシリテーターを務めていただきました。印象に残っていることはありますか?
李:ルールメイキングの対面イベントに参加するのは初めてだったのですが、リアルな熱量を見ることができて楽しかったですね。私自身は校則にただ従ってしまうタイプの生徒だったので、高校生が現状に疑問や課題意識を持って、主体的に行動する姿に刺激を受けました。ZOZOも社員の主体性を重んじているので、とても通ずる部分があるなと改めて感じましたね。
鹿子:私たち自身が刺激をもらうタイミングは多かったですよね。最上位目的を共有することや、お互いの考えの背景を知ることは、私たちも忘れてはいけないなと思いました。
篠田:ゲーム「ルールメイキング対話クエスト」の完成度が非常に高かったですよね。企業内のチームビルディングにも使えそうなくらいでした。
ーー教員ではない、民間企業の社員が生徒たちとの対話のグループに加わる意義も大きかったと思います。
李:私が担当していたグループの隣のグループの話ですが、教員の方が企業の方に「とても助かりました」と伝えていたのが印象的です。ルールメイキングの活動の中では、生徒と教員の意見が食い違ったり、不満や対立が生じたりすることもありますが、教員の立場では言及しにくい点でも、利害関係のない第三者の民間企業の社員であれば、客観的な立場から現状を整理しやすくなります。実際に、生徒が悩み事を相談していたところに、企業の方が「校長先生は、校則見直しについて◯◯と思っているんだろうね。じゃあどうしたら前に進むだろう?」というように中立の立場からファシリテーションしていたのを見て、教員と民間企業の両方が参加する価値を感じましたね。
ーーこれからもさらなるコラボレーションと共創価値を生んでいければと思っています。最後に、ZOZOさんの教育事業の今後の展望を教えてください。
篠田:KPIを置いてはいますが、数値にとらわれるのではなく、「目の前の子どもたちにとって、本質的に支援になっているのか?」を意識し続けながら、たくさんの次世代と接点を持っていきたいです。
鹿子:キャリアや自己選択といったメッセージも引き続き伝えていきますが、今まで以上に、アパレルというZOZOらしさを活かした教育事業を考えていきたいと思っています。ファッションや自己表現といったテーマは、生徒の方のニーズがあるかどうか分からず、これまで迷いが残っていた分野なんです。
李:初めての取り組みとして今年、ファッションの専門学校向けに、ZOZOUSEDの販売基準を満たさない商品を提供し、アップサイクルして社会課題を表現するプログラムを行いましたが、中高生への授業としてはまだチャレンジできていないところですね。
ーー校則にも直結する分野ですし、とても需要がありそうですね。
篠田:探究学習のテーマにファッションを置いてみるのもいいかもしれないですね。「スカートを一回折ることが誰かの迷惑になるのか?」と私も感じる一方で、学校は社会の一部であって、その場の全員にとって心地が良い状態も大切ですよね。難しい問いですが、こういったテーマの探究は小さなルールメイキングの繰り返しですから、その営み自体を面白いと思ってくれる次世代が増えてほしいです。その先に、「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」を実現できている未来があるのだと信じています。

新着記事
カタリバではルールメイキングに取り組む
学校・先生・自治体をサポートしています
すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。
まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。