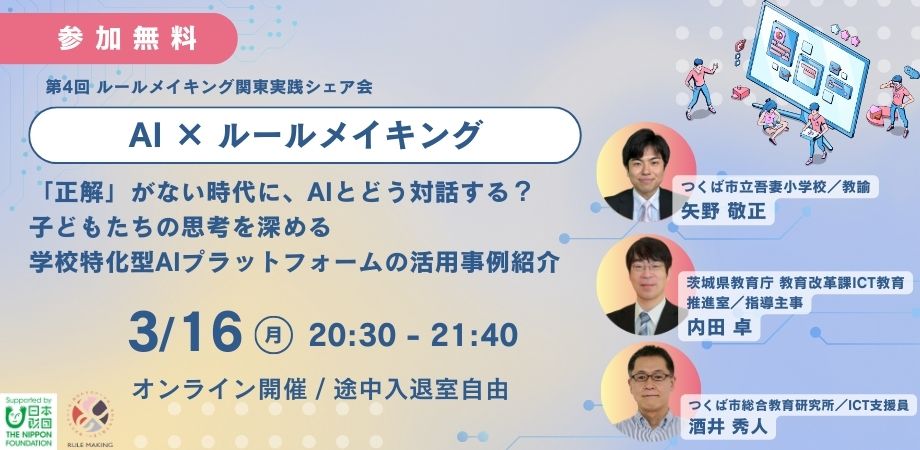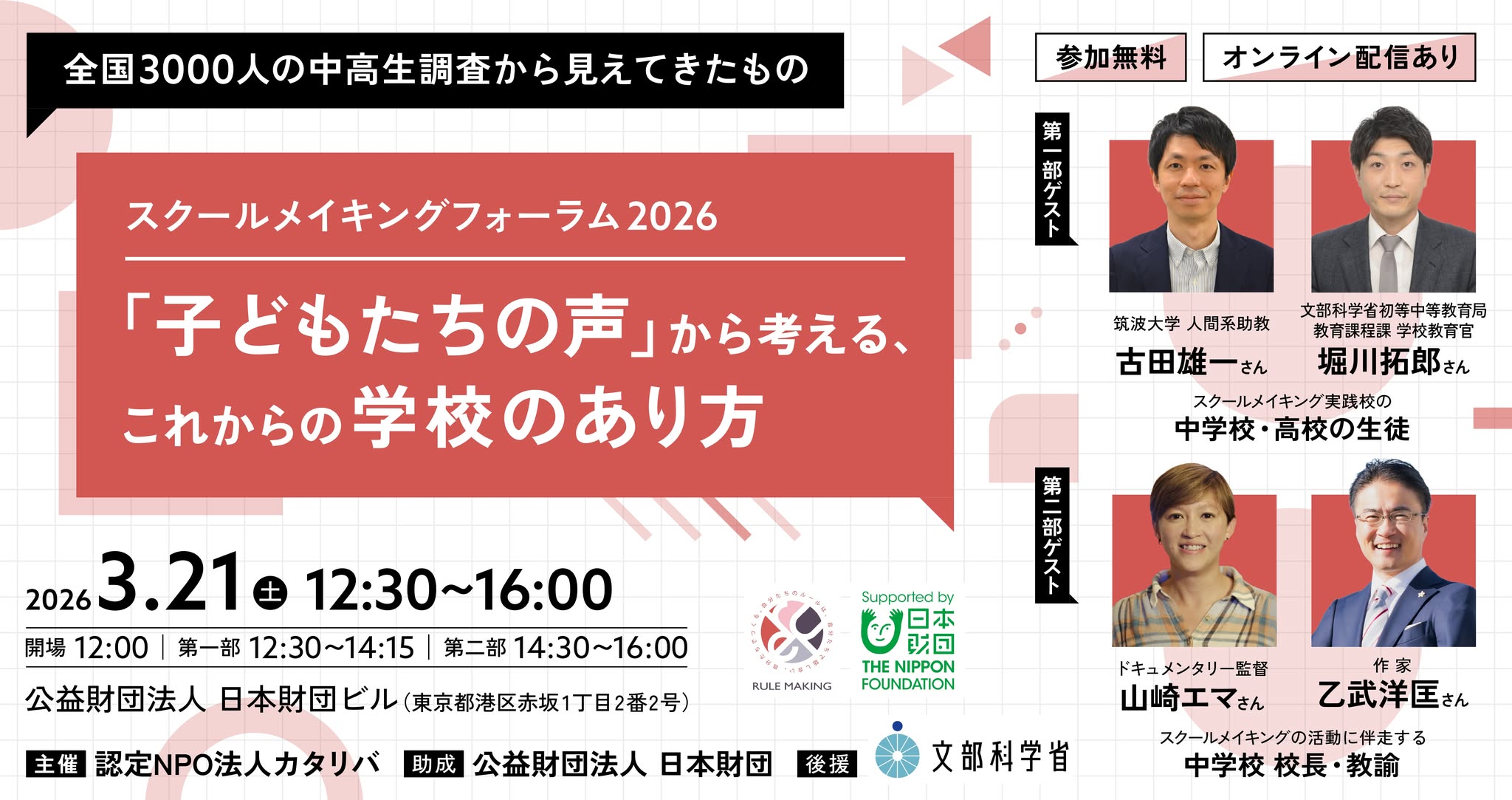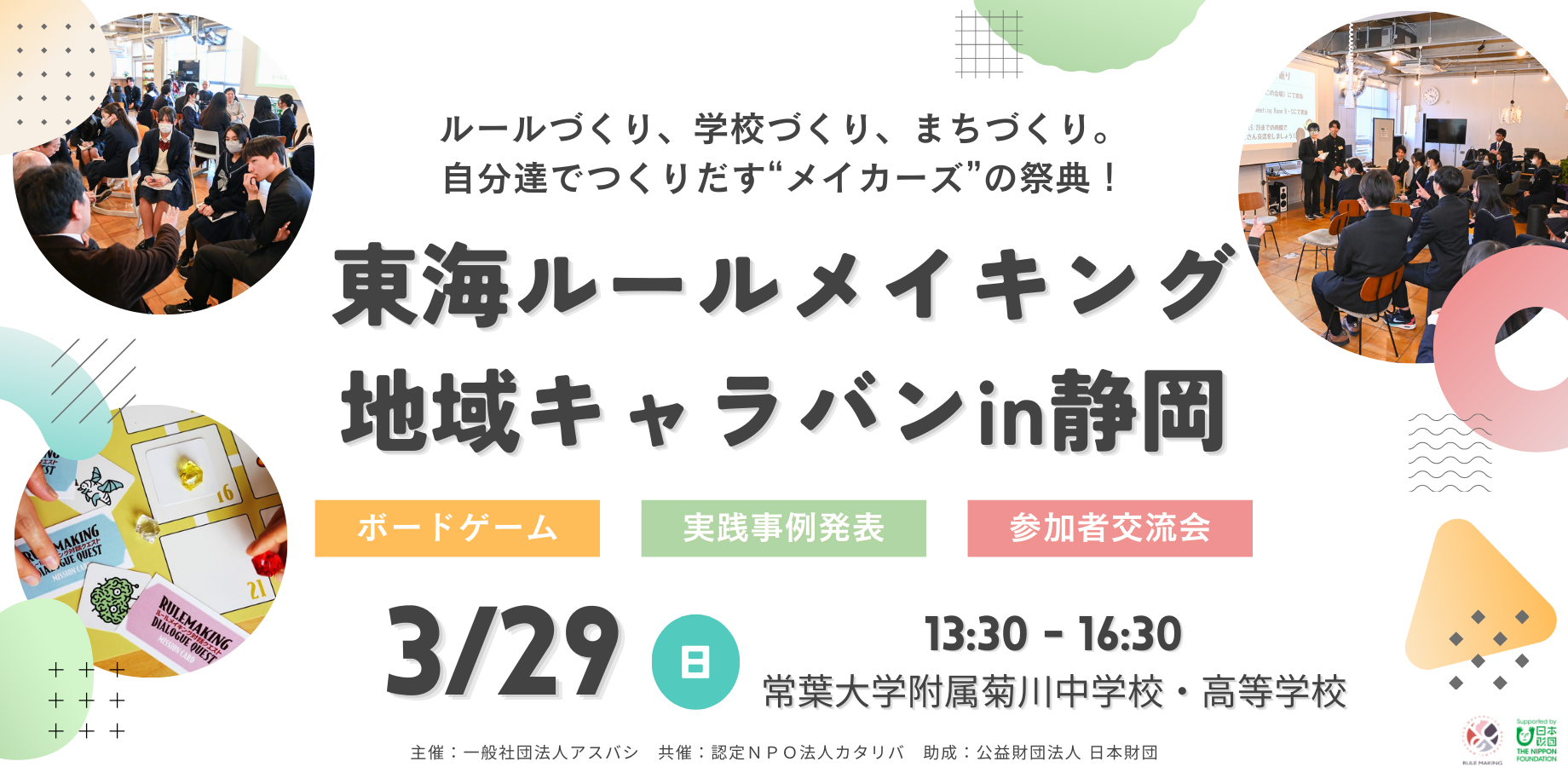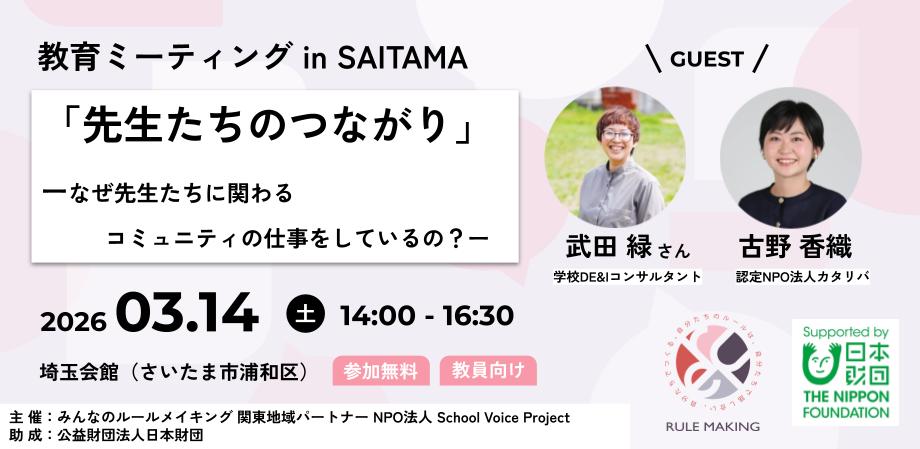
- お知らせ
- 【実践に学ぶ】初めて生徒会担当になり、ルールメイキング活動をはじめるために教員ができること
【実践に学ぶ】初めて生徒会担当になり、ルールメイキング活動をはじめるために教員ができること

こんにちは。みんなのルールメイキングです。
夏休みが明けた2学期から新しく生徒会が発足するタイミングで、ルールメイキング活動に取りはじめる学校もあるのではないでしょうか。そんな時、「初めて生徒会担当になり、ルールメイキング活動を始めるのですが、どういった手順で進めたらいいのでしょうか」「大切する観点はありますか」といった相談が寄せられることがあります。
そんな方のヒントとなるよう、今回は公式Webサイトで公開している記事の中から、
初めてルールメイキング活動に取り組んだ方のうち、同じく生徒会担当で「20~30代の若手教員」にスポットライトを当て、実践例をご紹介いたします。
▼仙台城南高等学校 教諭 尾形駿さん
仙台城南高等学校では、生徒会の生徒が中心となって2022年度に校則の見直しに取り組みましたが、教員側の理解を得ることができず、実際の見直しが実現しなかったといいます。生徒たちはその反省を生かし、2023年度に重点を置いたのは教員と生徒が話し合うプロセス。1年間のスケジュールを逆算して活動したことで、2024年度の生徒手帳に改正された校則の記載文を反映させることができました。
生徒会顧問であり、生徒会の活動を支えてきた尾形さんは当時をこう振り返ります。
活動が始まった当初を振り返ると、実は生徒会の顧問として、ルールメイキングは気が進まなかったのですよね(笑)やはり意見を通そうとしても、通らないという経験が何回もあり、正直衝突に近い状況の時もありました。それでも生徒の熱量が高く、私も動かされていたのですが、進めていく中でこちらが学ばせてもらうことがたくさんありました。
そして、他の教員からの活動への理解を進めていく工夫として、以下の点を挙げています。
教員側に理解いただけた理由の一つとしては、校則改正を目的にしなかったというところがあります。ルールメイキングの場を作ることによって、教員と生徒が一体となって学校の現状を考えるために行いますということを強調して伝えました。そうすることで、生徒たちが主体的に物事を考える力をつけることが目的となりますよね。
私自身は、生徒たちが考えていることを形にできるよう、他の教員の方との「橋渡し役」という立ち位置になっていたように思います。「生徒たちが考えたことです」と強調して伝えていくと、多くの教員の方が理解してくださいました。
最後に尾形さんは、ルールメイキング活動を通じた生徒の成長について、こう話します。
生徒会の中で、計画性を持って主体的に動ける力が身に付き、それが当たり前になったと言えるかもしれません。また生徒会の活動を受けて、学校全体がそういった空気感になっているように思います。自分で物事を考え主体的に解決していく力を、全校生徒に生徒会が見本として示せているのかもしれません。
▼佐世保市立山澄中学校 教諭 北武志さん
長崎県佐世保市教育委員会が校則の見直しに関するガイドラインを策定したことを一つのきっかけに、佐世保市立山澄中学校では生徒主体の校則の見直し活動に取り組んでいます。当初は「ルールはルールだから、きちんと守る必要がある」といった考えを持った生徒が多かったといいます。そういった生徒たちが「選択肢を広げる」という前向きな発想の転換ができるように、「生徒たちの考えをほぐす」という視点を大切にしてきたと振り返るのは、生徒会担当の北武志さんです。

山澄中学校では、2024年4月に校長から教員側に「生徒指導の観点から生活心得の見直しに取り組もう」という提案がありました。生徒総会でも、当時3年生のクラスから多様性などの観点を意識した校則の見直しの声が上がっていました。生徒の思いと、教員側の思いが一致したところに、教育委員会からの方針も出たことで、活動が本格的に始まることになったといいます。これと並行して、新年度から新しい制服が導入されるため、教員や保護者、生徒会の生徒で構成する「制服選定委員会」も開かれていました。
具体的にどのように活動を進めていったのか。北さんはこう話します。
2024年5月の生徒総会では見直されなかった項目があったので、生徒会に「もう一度見直せないか一緒に考えてみよう」と声をかけて、活動がスタートしました。
ただ、当時の3年生は私たち教員の考えをよく理解してくれる生徒で、最初は「決まりは決まりだから」と考えている子も多かったですね。校則に対して違和感を抱かず、みんなきちんと守れていましたから。
そこで私のほうから「でも見直していくチャンスだよ」と声をかけたら、「これって本当に必要なのかな?」「これは変えてもよいのかも」といった話し合いが始まりましたね。生徒会から各学級にも意見を求めて、オンラインのアンケート機能を使って「変えたい校則はありませんか?」と全校生徒にも投げかけました。
難しい点としては、「ルールはルールとしてきちんと守ろう」という意識がある生徒たちだからこそ、ルールの線引きが難しかったようで、最初は「見直すことはルールを壊す」ということだと捉えていました。そこで、「壊すのではなく、選択肢を広げる」という認識になれるように促すことが必要でしたね。
活動に対する他の教員からの不安の声には、こう向き合ったといいます。
「全てを生徒に任せる」という点においては、教員側からも少し不安の声もあったと思います。ですので、生徒ももちろん意見を言ってくれますが、全て任せるというよりは生徒と教員が一緒になってつくったという実感があります。髪を結ぶ位置について、教員側から「指定しなくてもいいのではないか」という意見もあり、そういった意見も反映させています。
▼那覇市立城北中学校 教諭 林達也さん
那覇市立城北中学校では、2022年度に校則の見直し活動に取り組み、生徒たちの進学先となる高等学校や地元の企業にヒアリングを実施しました。次の生徒会の生徒たちにも活動は引き継がれ、自分たちの学校の課題を考えて、全校生徒でChromebookのルール作りにも取り組みました。活動を支えてきた生徒会担当の林達也さんは、日ごろから生徒たちの当事者意識と市民性をはぐくむ関わり方を大切にしていると言います。林さんに、詳しくお話を伺いました。

林さんは2022年度に城北中学校に着任し、1年目の校務分掌が生徒会担当でした。そのときの校長から、「当時の生徒指導主事の先生と協力して、『生徒主体の学校づくり』を目指してほしい」と言われ、生徒たちと一緒に、校則改正やICT機器(Chromebook)のルールづくりなどに取り組みました。
当時3年生だった生徒会の生徒が全校生徒にアンケートをとり、本校にある課題を集約していきました。その上で、一部の先生で構成される企画委員会で集約した課題を提示して、「校則の見直しに取り組みたい」と提案したことで、活動がスタートしました。
生徒たちは、「①一人ひとりの人権尊重」 「②男女平等」「③コンプレックスの解消」「④心身の健康保持」の観点から、校則改正の意義を見出して進めていきました。例えば「スカートを短くしたい」という生徒の意見があったときに、上記4つの中でどれに該当するのかを生徒たちが考えます。校則を改正することが目的ではなく、最上位の目標を達成するための手段であるということ、そして自由には責任が伴うということを、生徒たち自らが、生徒総会で全校生徒に伝えていました。そして、生徒たちが校則を見直す「根拠」として考えたのが、学校だけで判断すると客観的ではないため、外部の意見を聞くということです。本校の進学割合が高い高校や、教育・医療・サービス業など高校卒業後に就職する近隣の中小企業・大企業にもヒアリングしに行きました。
ただ、活動に対する他の教員側の理解を得るのは容易ではなかったと言います。
1年間かけてこのプロジェクトに取り組み、最後に職員会議に改正の原案を持って行きました。生徒たちから「大企業や私たちの進学先も、ルールについてはこういったことを考えています」と根拠を示しながら、自分たちが校則について見直していく価値を伝えました。ところが、今と比べると、教員側からの反発も当時はまだ強かったんですね。
私も当時の校長も、他の職員に対して生徒たちの取り組みについてご理解いただけるように調整してきたつもりだったのですが、やはりまだ教員がルールを決めるという意識を拭い切れていなくて。「ここでは決定できない」と言われてしまいました。
私自身の詰めの甘さを痛感しました。そこから、「生徒たちはこんなことをやっています」「今後はこういうふうに動いていきます」といった情報を、私から他の教員に積極的に示すようにしていきました。
そして、ルールメイキング活動を通じ、「生徒会」の活動に変化が起きると強調します。
生徒会の活動が活発になりますね。「自分で学校を変えられる」という意識が芽生え、生徒たち自らが何かを企画したり、行事を作ったりするような動きが活発になっています。
本校の昇降口に「君も僕も生徒会 学校をつくるのも 僕らだ!」という生徒会のスローガンがあるのですが、私自身その言葉を繰り返し生徒に伝えています。まさしく、当事者意識と市民性を体現している言葉ですよね。こういった言葉から、生徒会のメンバーだけでなく、全校生徒にその気づきを与えられたらと考えています。
「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?
ルールメイキング・パートナーは、児童生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。
登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で校則をテーマに取り組んでいる学校や、児童生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。
新着記事
カタリバではルールメイキングに取り組む
学校・先生・自治体をサポートしています
すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。
まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。