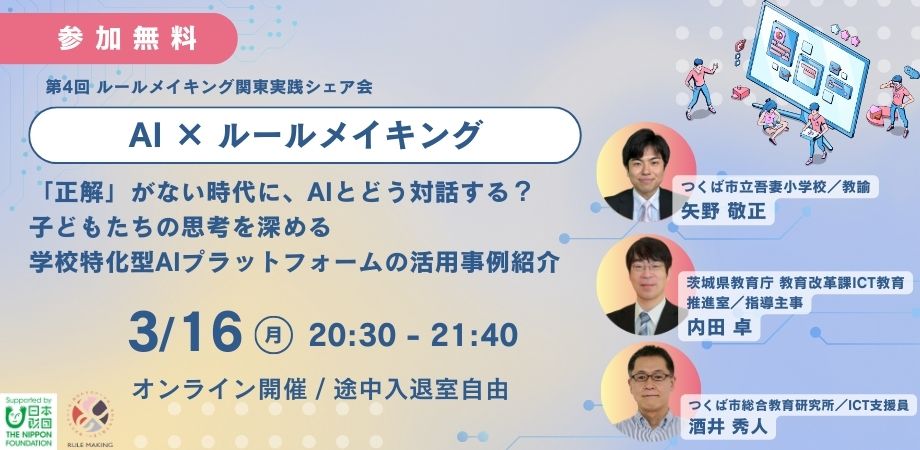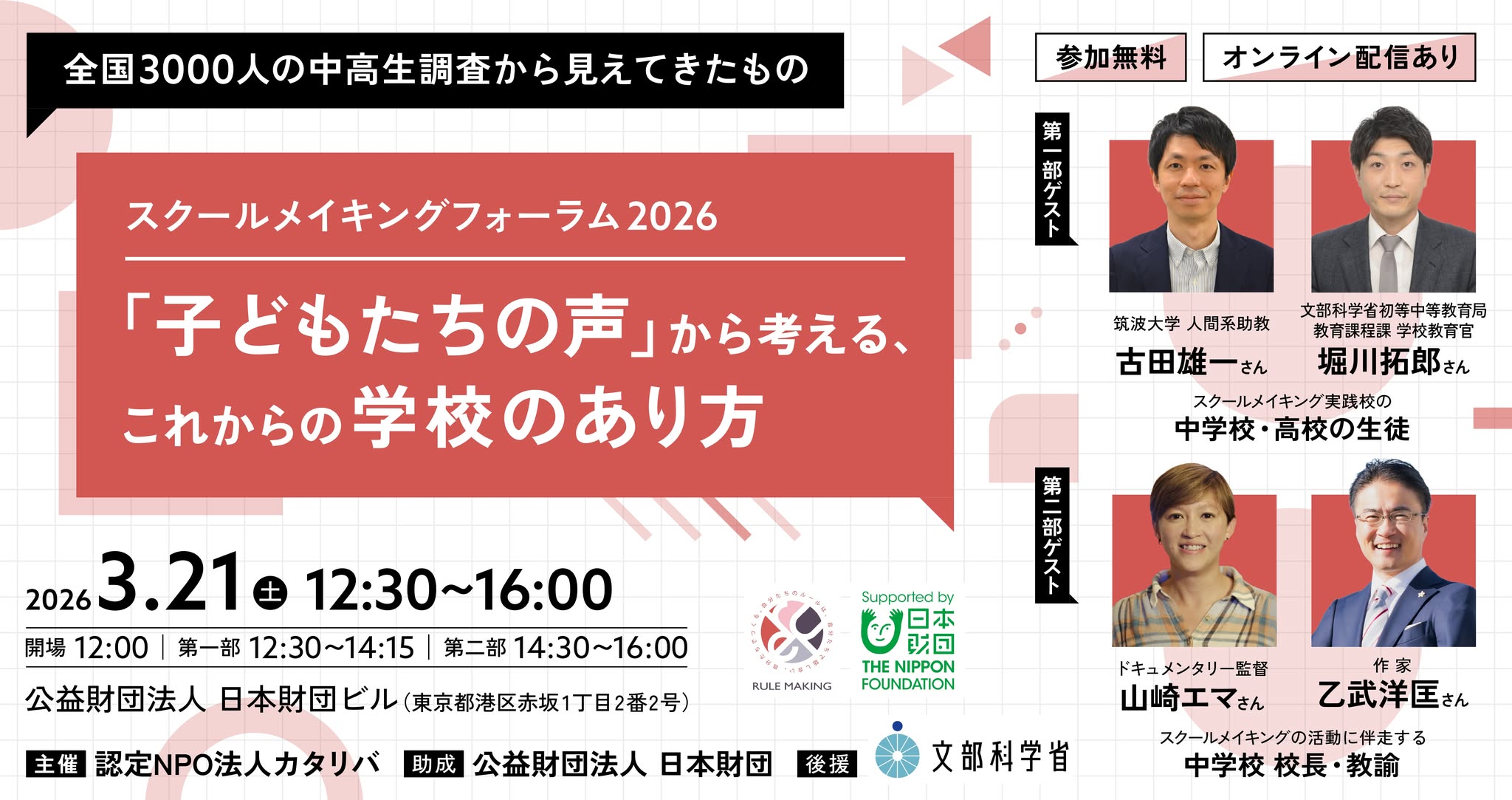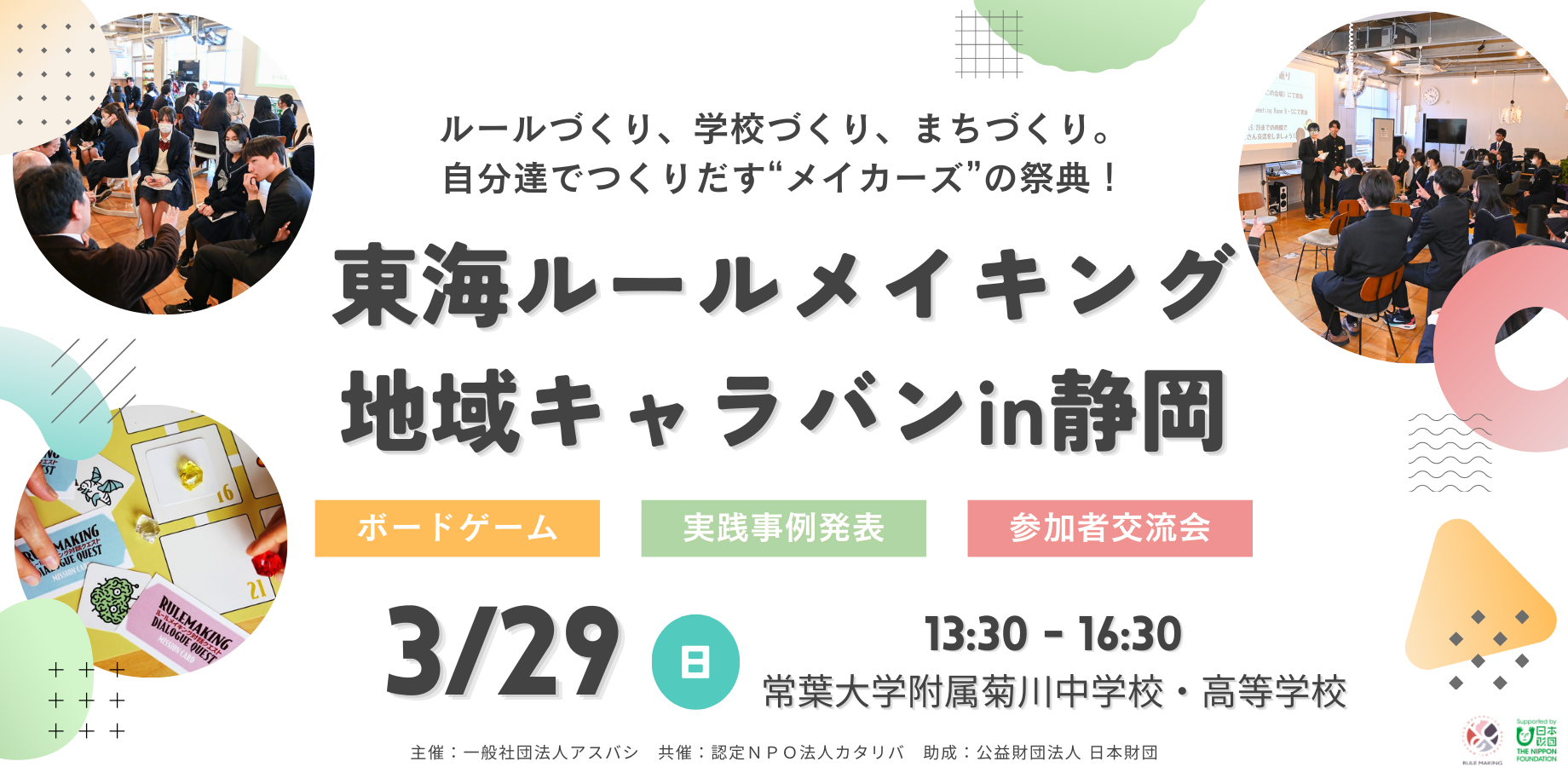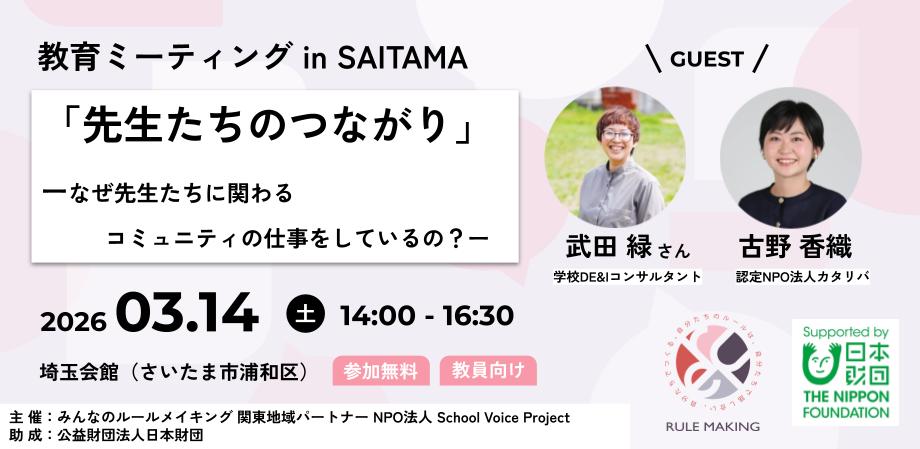
- インタビュー
- ルールメイキングを通して育まれた対話の土壌。全校生徒にとっての「最適解」を目指して
ルールメイキングを通して育まれた対話の土壌。全校生徒にとっての「最適解」を目指して
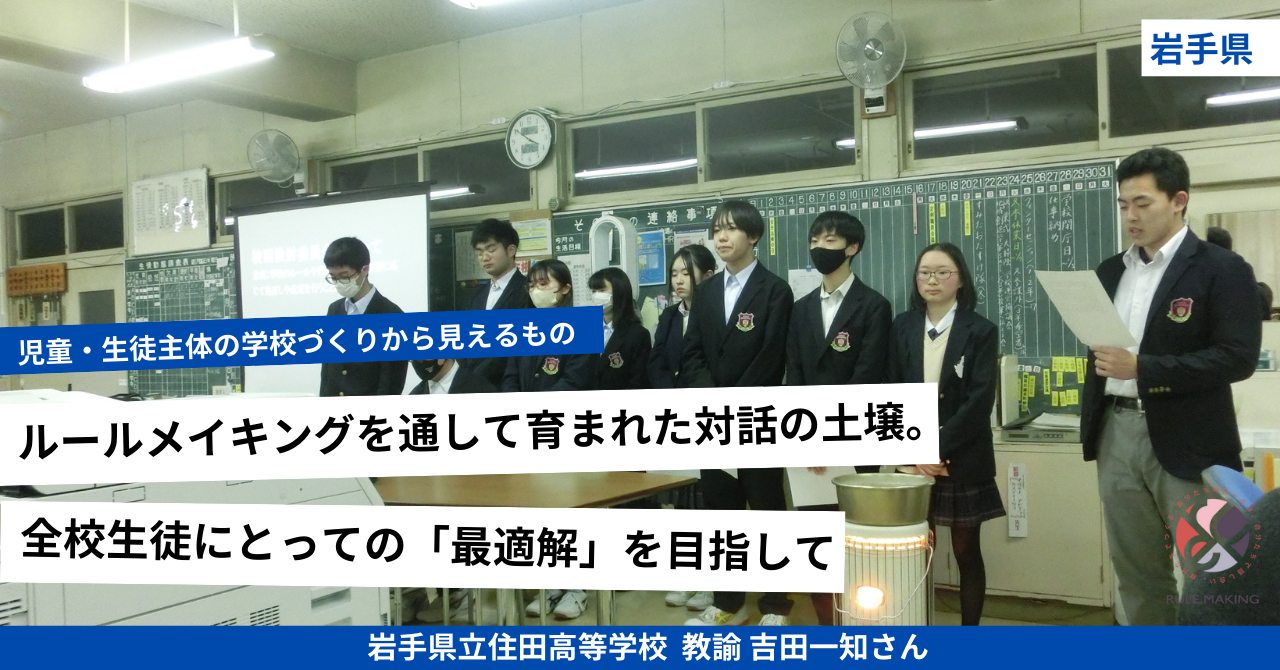
対話を通じて、児童生徒が中心となり学校の校則やルールづくりに取り組む「みんなのルールメイキング」。現在は480校以上の学校がカタリバとともに活動しています。全国では、さらに多くの学校でルールメイキングが実践され、校則見直しにとどまらない様々な場面で児童生徒が主体となった学校づくりに発展している学校もあります。
連載「児童・生徒主体の学校づくりから見えるもの」では、こうした実践の教育的意義をはじめ、教員や生徒の変化・成長を紹介していきます。また、児童生徒が参画する学校づくりの先にどんな景色があるのかを取り上げていきます。
2021年度に規定の制服ではなく、生徒たちが自分で制服を選べる「パーソナルユニフォーム」を導入した岩手県立住田高等学校。パーソナルユニフォール導入後にスカートの長さなど、どのように生徒に根拠を示していくかが課題となり、生徒主体となった校則検討委員会を立ち上げ、校則の見直しが始まりました。活動の理念づくりに取り組む中で、生徒たちに「対話する」土壌が育まれています。全校生徒にとっての「最適解」を導いていく過程を大切にし、活動を支える生徒指導主事の吉田一知さん(以下、吉田)に詳しくお話を伺いました。
※所属校、肩書はインタビュー当時のものです。

岩手県立住田高等学校 教諭
吉田 一知
2019年度に岩手県立住田高等学校に着任。2022年度より同校の生徒指導主事を務める。2024年度より校則検討委員会が立ち上がり、生徒たちが主体的に考え、全校生徒にとっての「最適解」が出せるように取り組みを支えてきた。
ーー貴校で校則の見直しに取り組み始めたきっかけを教えてください。
吉田:本校は、今から4年前までは指定の制服を導入していました。ただ、当時の生徒指導主事は、生徒から「制服が高い」「ジェンダー的な観点からも変えたほうかいいのではないか」という意見を受けていました。本校の制服をつくっている業者に早めに制服の注文を断らなければ、契約の関係上、2~3年は制服を変えることができなくなります。生徒の意見を踏まえて制服のあり方を見直すことになり、制服の注文を断りました。そうすることで、「絶対に変えなければいけなくなった」という背景がありました。
そこから、2021年度に教職員、PTA、生徒会の各代表を構成メンバーとした「制服検討委員会」を立ち上げ、1年間検討し、規定の制服ではなく生徒たちが自分で制服を選べる「パーソナルユニフォーム」という新しい学校着が導入されました。
パーソナルユニフォームが導入された時に入学してきた生徒が2024年度に3年生になり、全学年がパーソナルユニフォームを着用している状態になりました。そうすると、新しい問題が出てきたんですね。「ルールメイキング」という考え方が出てきたことを知っていたので、本校でも校則について生徒たちを中心に見直していこうという話が出てきました。2023年度末に職員会議で諮り、2024年度から校則見直しがスタートしました。
ーー新しく出てきた問題とは、具体的にはどんなものだったのでしょうか。
吉田:例えばスカートの長さです。パーソナルユニフォームを導入することになったときも、生徒の意見を取り入れ、スカート丈の長さは「膝が隠れる程度」 と決めました。ただ、だんだんとスカート丈が膝上になる生徒が出てくるようになりました。一般的な制服のカタログなどにも、膝まで隠れるようなスタイルで示されていることはほとんどありません。また、私自身も「膝が隠れる程度」でなくてはいけない理由が説明しきれないし、その根拠を示せる材料も持っていませんでした。本校は探究学習に力を入れているので、「根拠を示す」ということをとても大事にしています。そうであるにも関わらず、制服に関する決まりでは、他の教員も私も生徒たちに根拠を示せないのはどうなんだろうと思っていました。そのため、何のためにルールがあるのかを生徒たち自身で考えていく必要性を感じました。そうでないと、ルールを守れないだろうと。
ーーなるほど。2024年度春から実際に見直し活動をはじめたとのことですが、具体的にはどういったことから着手されたのでしょうか。
吉田:まずは私が2、3年生の生徒を対象にアンケートをとり、意識調査することからはじめました。「 ルールって何のためにあるんだろう? 」「ルールがなくても、実は学校生活は送れるのではないか」ということを生徒たちに一度考えてもらい、さらに本校にはどのような校則があるのかを知ってもらいたいという狙いがありました。
「校則はなくてもいい」「もっと自由でもいいのではないか」という意見が出るかと思ったら、意外と現実的な考えを持っている生徒が多く、「校則は必要だ」という意見が圧倒的に多かったです。 同時に、やはり校則は何であるのか、誰の役に立つものなのかを考えたことがない生徒も多かったですね。
その後、有志の生徒からなる校則検討委員会を立ち上げました。生徒会の生徒もいますが、生徒会とは別の組織です。私自身も「校則が変わる、生徒が変わる、学校が変わる みんなのルールメイキングプロジェクト」の本を読むなど、参考にしました。そこで例にあがっていたのが、同じ岩手県の大槌高等学校です。大槌高等学校では校則検討をする上で、まず理念を考えることから取り組んでいました。本校でも校則を検討していく上で、次第に方向がずれてしまうことがあると思ったので、最終的に立ち返る場所として理念を考えることにしました。
ーー校則検討委員会の皆さんで意見を出し合って、理念を決めていかれたのですね。
吉田:はい。最初は3年生3名、2年生3名の計6人の生徒からスタートしました。どんな理念であれば、学校生活がよりよくなり、活動できるかを考えて、何度も意見を出し合っていました。最終的に一人一人の個性を大事にして、それを認めていく学校をつくっていきたいという思いから、「生徒が個性を出せる学校」という理念に決まりましたね。本校の生徒募集ポスターに「わたしは、宇宙にただひとり」という言葉があります。そのため、生徒の個性を潰してしまうような校則は見直していく必要があるという意見になりました。小規模校なので、生徒一人一人に意識が向けられる環境にあるんですね。
その後、検討委員会の生徒たちからこの理念に決めた理由をきちんと全校生徒と教員に説明し、アンケートをとった結果、ある程度の了承は得られたところです。
ーー最終的に立ち返る理念が決まり、これから本格的に校則の見直しに取り組まれるのですね。
吉田:はい。ただ、アンケートを受けて多く出てきたのが、「個性って何ですか?」という意見でした。これについても校則検討委員会で話し合い、「個性って意味付けできないよね」という結論に至っています。意味付けできないから個性でもあると。それをまた全校生徒や教員に報告し、今後さらにアンケートを通して「個性って何だと思いますか?」というようなことを全校生徒に問いかけていけたらいいなと思っています。
ーーこういった活動をはじめるにあたって、教員同士の共通理解を得ることが課題になる学校もあると聞きますが、貴校はどうだったのでしょうか。
吉田:本校はそういった難しさはありませんでした。他の教員の中にも「根拠が必要だ」という考えがあったんだと思います。
私自身は正直、これまでは校則について考えたこともなかったんです。守る、守らないという以前に、私が学生のときは、意識の中心には部活動や勉強のことがあったので、深く考えることがありませんでした。教員になってからも、情けないことに若い時は「ルールだから守るんだ」という意識であり、その理由について生徒たちに大きな根拠は示せていなかったと思いますね。最終的には「進路のため」と済ませてしまっていたのではないでしょうか。
時代とともに、自分の中で少しずつ感覚が変わってきたと思っています。例えば探究学習でも、「そもそもなぜそういったことが起きるのか」を明確にすれば、自然と物事が決まっていくように感じています。社会に出たときに、生徒たちが「しっかりと自分の持っている力を発揮して生きていくこと」が教育の一番の本筋だと考えた時に、例えばバイトが許可されている時間は「夜6時まで」だけど、ではなぜ「夜7時まで」だとだめなのか。ジャージで授業を受けることにどんな影響があるのかなど、決められた「当たり前」が不思議に思えてきたんですね。
ーー吉田さんの中にも違和感が出てきたのですね。校則検討委員会の活動を通して、生徒たちの変化はどのようにお感じになっていますか。
吉田:活動の当初は、生徒たちにとって「意見を言う」ということが容易ではありませんでした。最初から全て生徒に任せるという方法もあると思いますが、難しいことでもあるので、最初は私から「何でもいいからまずは言ってみて」「今日はこんなことを考えているんだけど、どうかな?」という声かけをしていました。私のほうで生徒を指名して、意見を言ってもらい、「じゃあ次の人はどう思う?」というようなやりとりをくり返すうちに、誰かが言ったことに対して、他の人も自分の意見を伝えることができるようになりましたね。徐々に対話的になってきていると思います。また、1年生に発言できる生徒が多かったこともあり、いたる所でそれぞれ意見交換が行われ、最後に手を上げて全体に意見を共有するという形になってきました。
日ごろの探究学習も含めて、みんなの前で話すという経験が生徒に増えてきているので、その積み重ねも大きいのかもしれません。2024年度中に、生徒たちの力で進めていく土台をしっかりと作っていくことが大切だと考えています。
これから正反対の意見同士がぶつかることもあると思うのですが、「こっちの意見が多いから、これにしよう」というスタンスではなくて、みんなが納得のいく最適解を出していくことをしっかりと見つけてほしいですね。
生徒たちの中で、今はとにかくいろんな立場の人に意見をもらおうという姿勢になっています。視野を広げていきたいと思っているのはないでしょうか。そのため、生徒や教員だけではなく、保護者の意見ももらいたいという話になっています。校則については保護者の方々も分からないものが多いです。本校は生徒の身分証明書の裏にQRコードがついていて、それを読み込むと全ての校則が読める仕組みになっています。こういった機会を通して、生徒たちが保護者の方とも校則について考えたり、会話したりしてくれることを期待しています。
ーー活動を通して、生徒に期待することはどんなことでしょうか。
吉田:意図的に私のほうから「はじめますよ」と伝え、それに生徒たちが乗っかってきてくれた部分もありますが、最終的には生徒たちの責任のもとで判断し、きちんと最適解を出してもらいたいと思っています。そのために、しっかりと根拠を示していってほしい。今は校則検討委員会が中心となっていて、全校生徒の中には「何をやっているのか分からない」「面倒くさい」と思っている生徒もいると思いますが、そういう生徒も上手に巻き込んでいってほしいですね。校則検討委員会というコミュニティを、どう学校全体のコミュニティに広げていけるのか、悩んだり試行錯誤したりしていくことが大切だと思っています。そのためには、教員が「生徒たちはできるんだ」という認識のもとに、活動を進めていくお手伝いができればと考えています。
「ルールメイキング・パートナー」にあなたも参加してみませんか?
ルールメイキング・パートナーは、生徒主体の校則見直しや学校づくりをはじめたい、既に実践している小・中・高校の教員が無料で参加できるコミュニティです。
登録には学校承認は不要で、教員個人での申込みが可能です。探究学習で生徒が校則をテーマに取り組んでいる学校や、生徒を中心にした学校づくりに関心がある全国の教員を対象に「ルールメイキング・パートナー」を運営しています。個別相談や情報収集のみでもご利用いただけますので、お気軽にご参加ください。
新着記事
カタリバではルールメイキングに取り組む
学校・先生・自治体をサポートしています
すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。
まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。