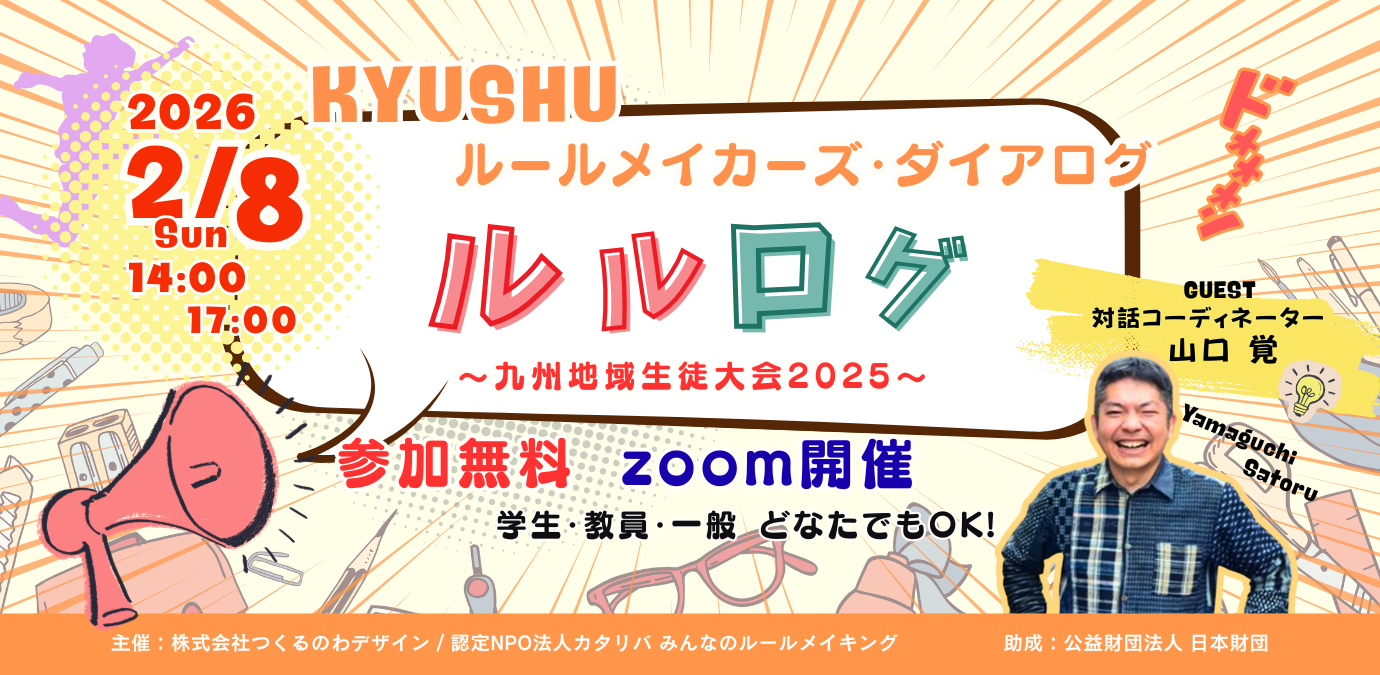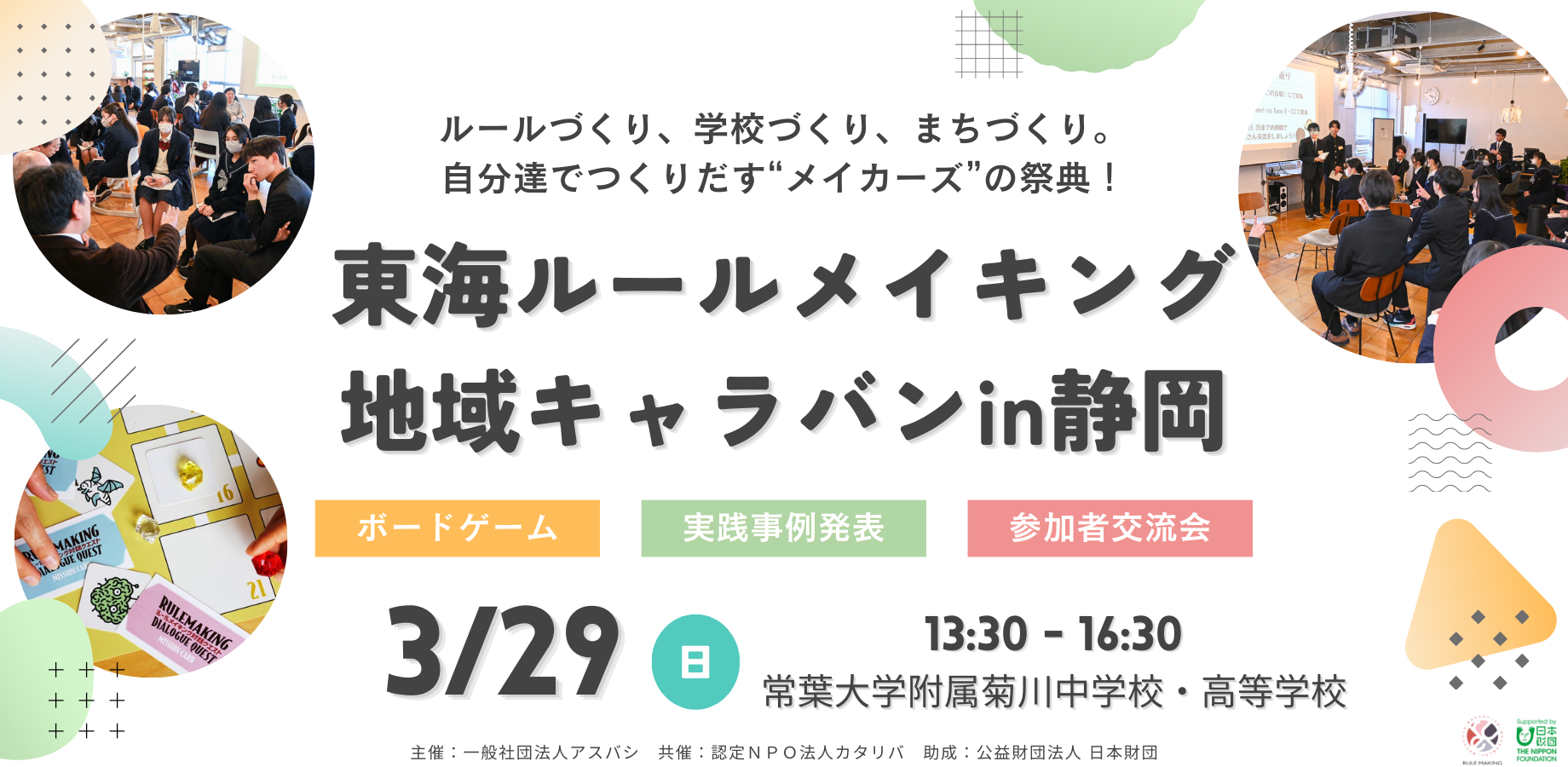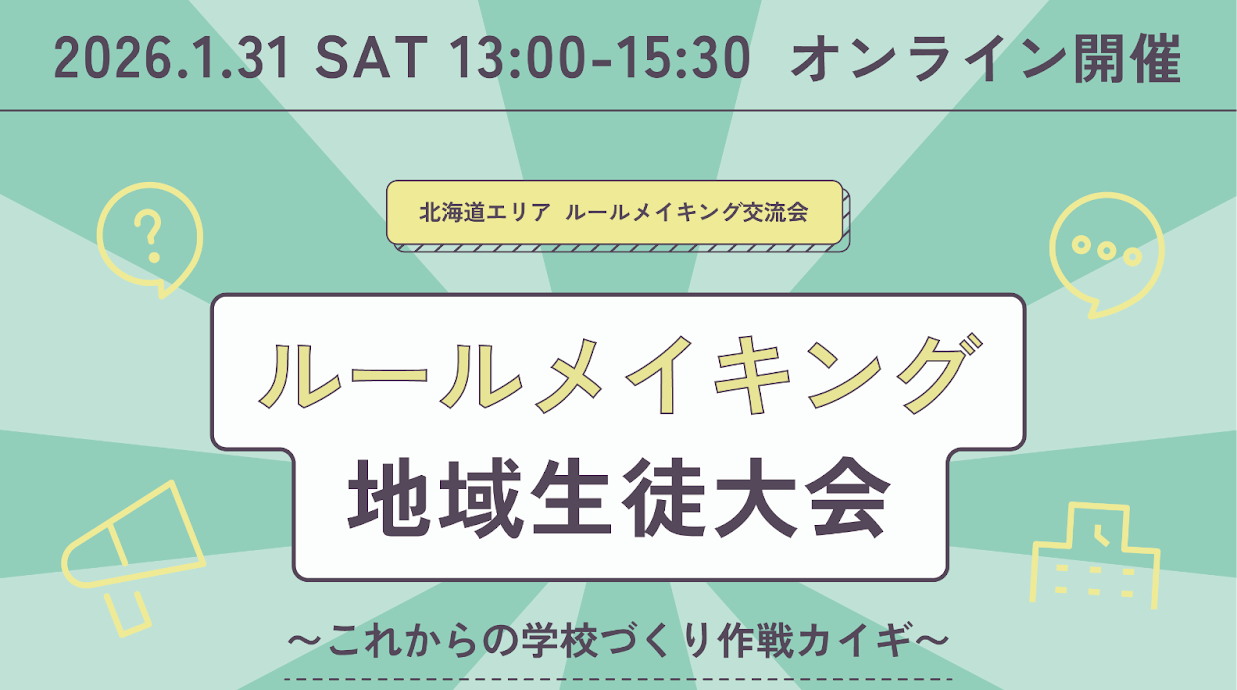
- イベント
- 「イベントレポート」2月2日にルールメイキング関西地域生徒大会を開催!関西地域の生徒や先生らが集結!!
「イベントレポート」2月2日にルールメイキング関西地域生徒大会を開催!関西地域の生徒や先生らが集結!!

こんにちは、大阪夕陽丘学園高校(OYG)のふーちゃんです!私たちのルールメイキングの活動は生徒会のメンバーで行っています!私たち、OYG生徒会は、学校は第一に誰もが安心安全な環境でなければならないと考えています。「校則で決まっているから」ではなく、自分たちで考え判断するチャンスにしていくことで学校が目指す生徒像である「自律した学習者」に近付くと思っています。
関西創価高校のかわくみです!普段私たち関西創価高校は、「校則委員会」というルールメイキングをする団体を中心に、学校にいる人全員が心地よく過ごすためのルールメイキング活動を行っています。
私たちは今回、過去に開催されたなかでも最大数の参加者となったルールメイキング関西地域生徒大会を運営側や、発表者として参加してきました。
関西地域生徒大会が開かれたOYGには、ルールメイキングに取り組む大阪府や京都府、滋賀県の中学校、高校計11校が一堂に会し、互いにポスター発表や対話などで交流を深めました。
※今回は関西地域生徒交流会に参加した高校生の2人がレポート記事を書いてくれました。高校生ならではの視点でイベント当日の様子をお届けします!

当日に向けて準備開始
関西地域生徒大会では、各校の生徒がこれまでの取り組みをポスターを用いて発表する「ポスター発表会」が行われました。各校の生徒がこの日の発表に向けて、それぞれスライドの作成に力を入れてきました。
会場校であるOYGでは、開催当日の2週間ほど前から準備を開始。参加者に楽しんでもらえるような工夫もしました。開催日が2月2日の節分ということで、「ルールメイキング的福は内」(うまくいっていること)・「鬼は外」(困っていること)を参加者で共有するため、ポスターを作成しました。
当日は、参加者のみなさんが自分の考えを付箋にたくさん書いて貼ってくれました!!「仲間が増えた」「ルールメイキングに対して肯定的な意見が増えたという声がありました。一方で、「立場が上の人の理解が得られない」といった声も。みんなの考えが詰まった、とても素敵なポスターになりました。

学校間交流プログラム:「ルールメイキング対話クエスト」
最初のオープニングで、大人も子どもも気持ちよく過ごせるように、「いい子のフリをして大人が求めている答えを言おうとしない!」「ニックネームで呼ぶ」などのグランドルールが設定され、みんなで共有しました。
オープニングを終えると、学校や年齢が異なる3~4人程度のグループを組み、「ルールメイキング対話クエスト」というゲームを行いました。「ルールメイキング対話クエスト」とは、認定NPOカタリバが制作した世界に一つだけのボードゲームで、一人ずつ配られた内容が異なるミッションカードに従い、クリアを目指すゲームです。

1回目のプレイでは、ミッションカードをお互いに隠した状態で行われ、自分がクリアするためには相手の妨害をしないといけないこともしばしば…。制限時間内に全員がゴールできないグループも多くありました。
ところが2回目のプレイで流れが一転!今度はミッションカードをお互いに見せ、グループ全員でゴールを目指すルールに変更されました。
1回目と比べ、お互いにやりたいことがわかっているからこそ、協力や連携が生まれ、結果ほぼすべてのグループが時間内にゴールを達成しました。ここでゲームの主催者からこの「ルールメイキング対話クエスト」で伝えたかった本当の目的が話されました。それは、「お互いのことや行動の理由、置かれている状況を知り、みんなで対話を通して合意形成をすることが大切」ということでした。ゲームに参加した生徒は、「はじめは何を目的にゲームをしているか分からなかったが、ゲームをやって、相手の行動の意味や目的を考える大切さを知った」「日頃自分が理解できなかった人の意見や主張も、もっと深く考えなければならないと思った」などの意見がでました。
また、メンバーはその時初めて顔を合わせるので、1回目のゲームでは、少し緊張した空気が流れていましたが、2回目のゲームでは、思いやりが自然と生まれ、笑顔が飛び交っていました。
ポスター発表:「お互いのルールメイキングを知る」
ここから参加校それぞれにに1教室ずつ貸し出され、主にスライドを使い、各学校が行っているルールメイキングについて発表をしました。
発表の回数は計3回あり、発表校ではない参加校も他校のルールメイキングを知ることができ、学びの多い時間となりました。また学校によって発表の仕方も様々工夫されており、特に印象的だったのは体験型の発表です。その学校では、ルールメイキングで制服のデザインを変更しており、実際に変更された制服と前の制服を触って、素材など利便性の違いを直接知ることが出来ました。体験することで、ポスター発表の内容に説得力が出るようになり、有意義な時間でした。さらに発表時間の中には、質疑応答の時間があり、その場にいる人たちで対話会を行う学校もありました。

通っている学校、立場、年齢など、普段なら関わる機会のない人たちと、ルールメイキングを通して対話を深めることができました。
大阪府教育長水野達朗さんのトークセッション:「ルールメイキングの在り方」
発表が終わると、再び参加者は体育館に集まり、全体で結果交換や感想を共有しました。その中で、大阪府教育長である水野達朗さんが話をされました。
水野さんはルールメイキング活動について「”変えること”を目的化するのではなく、”生徒自身がどういった学校を目指すのか”を第一に進めて欲しい」「校則を変えることで満足するのではなく、必ず目的を持ち、それを忘れず活動を続けていくことが大切」と強調していました。ブラック校則など、形だけ残っている校則も多い中、声をあげ、自らが動いて考える「ルールメイキング」をしていく大切さを改めて考えるきっかけとなりました。

対話ワークショップ:グループに分かれて1日を振り返る
ついに最後のワークになりました。振り返り、アクションカード記入の時間です。振り返りでは、4人1組となり、この会の感想・印象に残ったことなどを話し合いました。アクションカードは、「今日の学びを明日以降につなげたい」という思いから作られました。
参加した生徒から多く挙げられたのは、「いわゆるブラック校則を変えるのではなく、みんながより過ごしやすくするために校則を考えるということを伝えたい」「家族や友達にルールメイキングについて話してみる」といった声です。
他にも、「ルールメイキングが成功したか、しなかったかではなく、生徒主体で取り組んだことが大切だと分かった。結果が全てじゃない」「みんなが安心して過ごせる学校・社会にするために対話の文化を広げる」などといった思いも共有されました。
関西地域生徒大会を通して
今回の関西地域生徒大会を通して、年齢を超えて、ルールメイカーや、ルールメイキングに興味を持つ人と、ゲームや発表、対話を通して交流しました。特に最後に行った全体での振り返り時間の対話は、それぞれがその日学んだ知識や感想を共有し、今後どのように自分たちで行動するかの決意を話すことができました。その対話の輪の中には先生も参加し、生徒が積極的にまだグループに入れていない大人や先生を誘う姿も見られました。参加校や人数が多い関西大会だからこその盛り上がりや学びが沢山あり、充実した1日となりました。

新着記事
カタリバではルールメイキングに取り組む
学校・先生・自治体をサポートしています
すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。
まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。