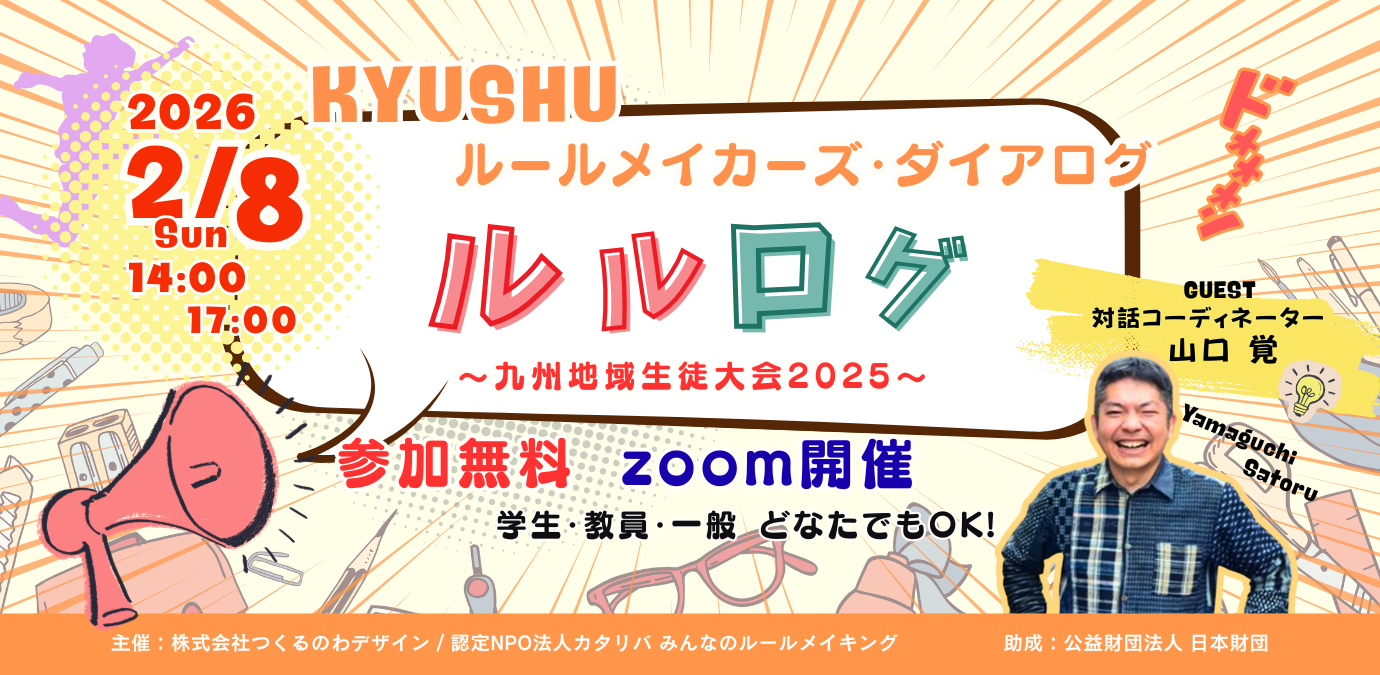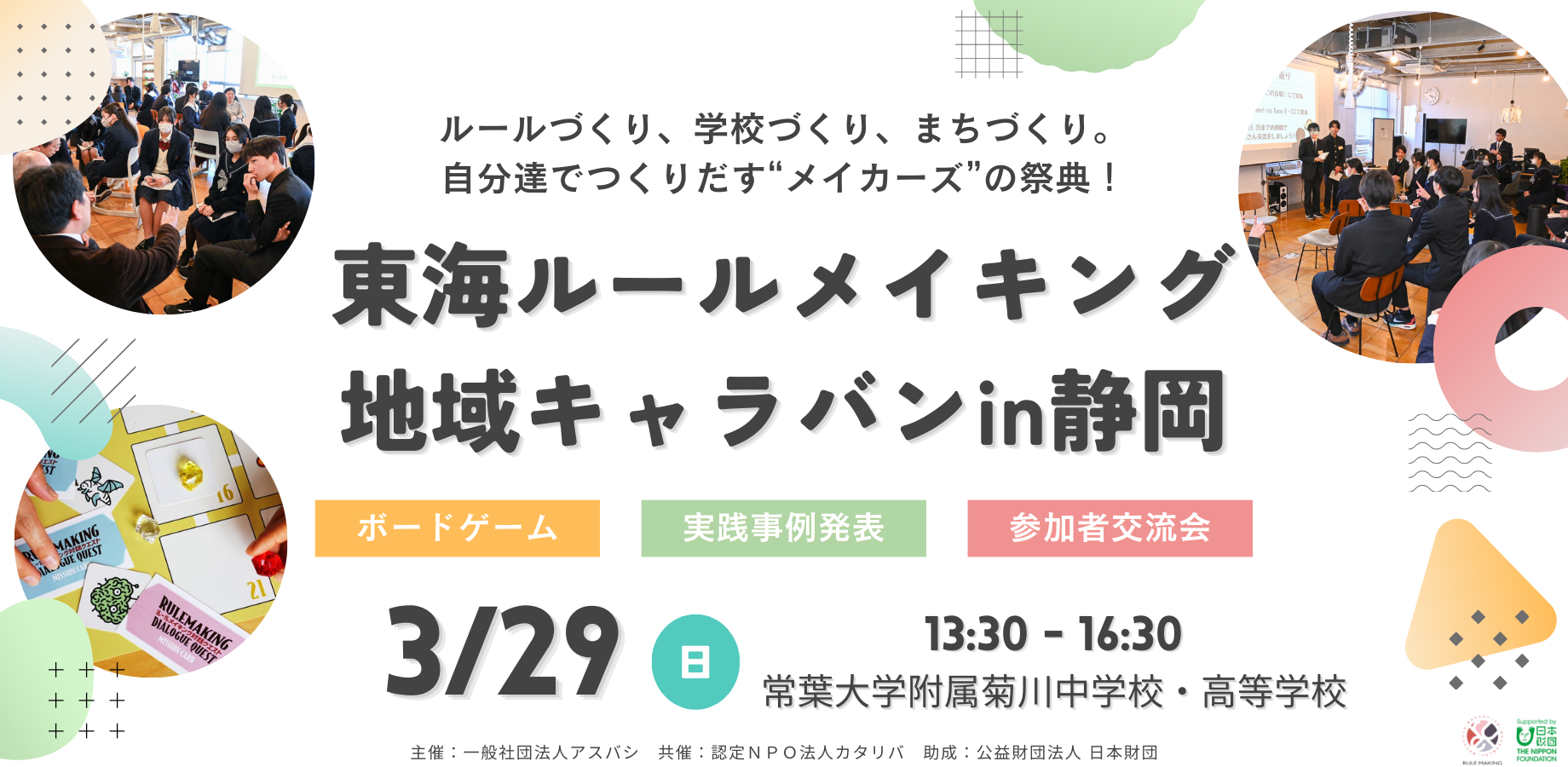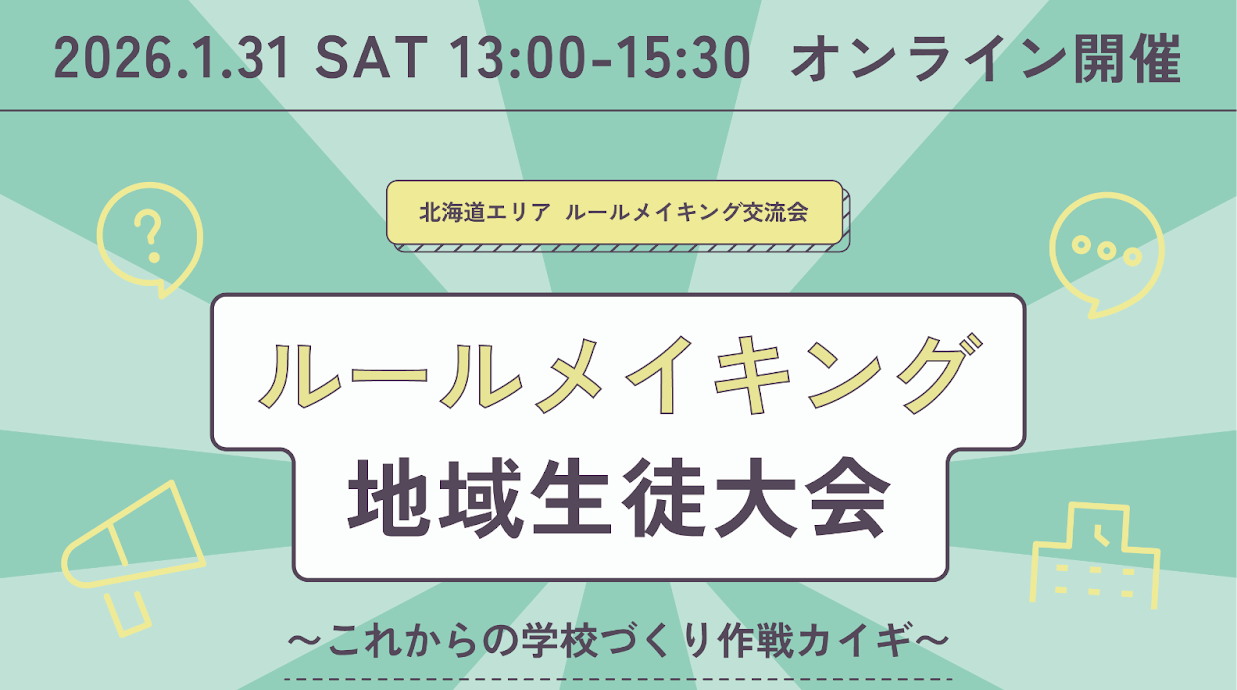
- インタビュー
- 声に出す勇気で変わる校則 生徒と教師が協力して作る学校
声に出す勇気で変わる校則 生徒と教師が協力して作る学校

ルールメイキングは、生徒が中心となり教員など学校の関係者と対話しながら校則・ルールを見直していく取り組みです。「校則・ルールが変わる」という結果だけではなく、立場や意見の異なる違う人との対話を通じて納得解をつくるプロセスを大切にしています。
連載企画【ルールメイキングから始まるわたしの一歩】では、ルールメイキングやそのイベントに関わった生徒や卒業生、教員から思いを聞くことで、ルールメイキング活動の先にあるものを考えていきます。
今回お話を聞いたのは・・・

福井市大東中学校・3年生
笹岡くるみさん
2023年から校則改正委員会に所属。
ルールメイキング・サミット2024に招待生として参加。

福井市大東中学校・3年生
長野晴さん
2023年から校則改正委員会に所属。
ルールメイキング・サミット2024に招待生として参加。

福井市大東中学校・教諭
土成永侑さん
特別活動・生徒指導の担当教員。
生徒と共にルールメイキングの活動に励んでいる。
「自分たちに必要なルール」を生徒が探す。TPOも取り入れた校則づくり
ーールールメイキングの活動を始めたきっかけを教えてください。
笹岡)中学校に入学すると、校則で許可された髪型は1種類しかないなど、厳しい校則が多くありました。「多様性を尊重する時代になってきた中で、そういうルールは時代に合っていないのではないか」と思ったことがきっかけです。
長野)私は他学年との差を感じていました。ルールとしては明確にはなかったものの、触覚ヘア(前髪の横の髪を伸ばし、顔に沿うように作るヘアスタイル)を3年生は見過ごされているのに、1年生はできないという状況があって、平等じゃないのはおかしいと思っていました。
ーー学校として校則見直しの活動が始まった経緯を教えてください。
土成)「ブラック校則」という言葉を耳にするようになったころに、教員の間で学校のルールを見直してみると「自分たちの学校も同じ」という意見が出てきました。そこで生徒たちにモニタリングしてみると、同じように感じている生徒が多かったので「このタイミングで手をつけていかないと、変えるきっかけを失っていく」と思い、校則見直しの動きが始まりました。
笹岡)最初に先生から「校則改正委員会」を設立するというお話がありました。「学校を変えたい」と考える30人ほどが参加する形で活動が始まり、週2回話し合いの時間が設けられてきました。委員会では「校則を変えるにもすべてを自由にするのではなく、TPOやマナーもわきまえたルールを作る必要がある」と考えていました。そこでまずは全校生徒で「TPOとはどんなものか」を話し合うところから始めました。
長野)まずは1から全部校則を見てみて、違和感がある校則について先生方と「今の現状に必要なのか・必要じゃないのか」を考えました。その上で「この校則がなくても、学校生活は大丈夫」と考えられるものを変えていきました。
ーー校則を変える過程の中で大変だったことはありますか。
長野)靴下の色についての決まりを考える時に「どの色なら制服に合うか・TPOに合っているか」ということを考えることが大変でした。周りからは「何色でも良い」と言われていましたが「制服に合わない色があるかもしれない」と考え、適切な色を考えるようにしていました。
土成)「校則を変えられる」という言葉にとらわれて、「校則改正委員会に入れば自由に何でも好き勝手にできる」と考える生徒もいました。それに対して「守らなきゃいけない一線はあって、そこを超えることは違うんじゃないか」と考える生徒もいて、笹岡さんと長野さんは生徒同士の異なる意見や、自分の思い通りにしたい生徒と教員の意見の違いをすり合わせることに苦労したのではないかと思います。
私自身は二人の話を聞くようにしていましたが、好き勝手している生徒に表だって「そういう考え方は違う」と教員の立場で言ってしまうと、その時点で「校則を変えられる」というムーブメントがしぼんでしまうので、あくまで彼女たちが自分たちの正義感で言葉にできる環境づくりを心がけていました。
ーールールメイキングの際にどんなことを意識していましたか。
長野)普段なら先生方が司会をするような場面でも、委員である生徒が司会をするようにしていました。そうすることで、他の生徒も意見を出しやすくなり、先生と生徒が対等な立場で、校則改正ができるようになりました。
土成)本校は500人規模の学校で18学級あり、各クラスでTPOやマナーを学ぶ活動を10回行いました。生徒たちは様々な視点から、校則をどう改正すべきかを考えました。加えて、学校という閉じられた空間にいる生徒や教員は社会の常識と感覚がずれているという危機感もあったので、保護者や地域の事業者にもアンケート調査を実施し、社会の常識を反映した校則改正を目指しました。また、笹岡さんと長野さんは同じ時期に職場体験も行っていたので、「世の中に出て働くとはどういうことなのか」も学び、ルールメイキングの活動に反映させてくれました。
結果ではなくプロセスが大事。変わり始めた学校の雰囲気
ルールメイキング・サミットは、認定NPOカタリバ「みんなのルールメイキング」が主催するイベントです。全国で校則見直しやルールメイキングに取り組む中高生100人が一堂に会し、地域や学年を超えたルールメイキングの仲間や社会で活躍するルールメイカーと出会い、対話し、学びを深め、発信する機会となっています。
ーールールメイキング・サミット2024に参加した経緯を教えてください。
土成)ルールメイキング・サミットについて案内いただいたものの、東京開催かつ、進路を決めるテストの3週間前のタイミングだったので断るだろうなと思いながら、2人に伝えました。すると2人とも「このタイミングが最後のチャンスだから、行きたい」と返事をくれました。
笹岡)自分たちの周りでは校則改正をしている学校をあんまり聞いたことがなかったので、ルールメイキング・サミットに参加することで、他県から来る人の意見をたくさん聞けることや視野を広げられることを期待していました。具体的には、誰一人取り残さないためのヒントとして、全校生徒の意見の取り入れ方や、「細かいルールだと縛られる。でも曖昧だと判断が難しい」という背景から来る常識や暗黙のルールの線引きについて学びたいと思っていました。

ーー実際にルールメイキング・サミットに参加して感じたことも教えてください。
笹岡)自分の意見をはっきり話すことはあまり得意ではありませんでしたが、サミットで他の生徒がうなずきながら自分の意見を聞き、共感してくれたので、自分の意見に自信を持つことができました。自分たちと似た活動をしてる人たちの意見や現状、頑張っていることを知れて共感できたことが嬉しかったです。
長野)サミットに参加したメンバーから「先生があまり協力的ではない」という話も聞いて、私たちが活動できていることが当たり前ではないことを知りました。それから、他のルールメイカーの活動内容を聞いて、同じように悩んでいることを知れたことが良かったと思います。

土成)サミットに参加するまではルールメイキング・サミットに来る生徒は、ものすごく意欲的で主体的な印象を持っていたので、2人がその中に入って、自分たちがやってきたことや学んできたことを発言して表現できるのか不安に感じていました。しかし、グループ活動が始まったとき、彼女たちが頑張って最初に話し始めた姿や、2人と同じグループだった他の生徒が意見を分かち合おう、共感しようとしてくれている姿が見えたので安心しました。休憩時間になってからも「私の学校には~~」とそれぞれの校則に関する話が生徒同士で続いていたことも印象に残っています。
笹岡)私たちの学校ではアンケートや話し合い活動くらいしか実施したことがなかったのですが、話を聞いていると、他校ではたくさんのユニークな方法で意見を取り入れていました。例えば、指定の体操服を変える時にモデルを募り、体育館でファッションショーをして決めたそうです。周りの注目もひけるため、委員会のメンバーだけで決めることなく、自然と全校生徒全員で決められるような方法になっていて、良いなと思いました。

ーールールメイキング・サミット後にどんなアクションを起こしましたか。
笹岡)サミットに参加してからは、先生方に対しても疑問に思うことをちゃんと言えるようになりました。例えば、冬場に女子生徒はタイツを着用しますが、体育のときは着用できず着替えが間に合わないという問題がありました。「着替えの時間のことも考えると、スカートの下に体操服の長ズボンを履いても良いのではないか」という意見がたくさんあったので、それを先生に伝えました。結果として、ルールを変えられませんでしたが、校則改正委員会ではない子たちからも、意見を言ってもらえたので、雰囲気が変わってきていると思います。
土成)2人が教員に考えを伝える際の伝え方も変わってきたと思います。「私たちはこう思うけど、大人から見たらどうなんですか」「これは社会に出たらどういう風に思われるんですか」と以前よりも意見の伝え方が上手くなったと感じています。
一度行動することの大切さ 繋いでいくルールメイキングの考え方
ーールールメイキングの活動全体を通して感じたことを教えてください。
笹岡)自分自身が委員長という立場だったこともありますが、周りの人も自分たちを頼ってくれて、意見をたくさん言ってくれる人がいたので、そういう人たちのためにも頑張ろうと思えるようになりました。
長野)校則を変えていく中で、今まで以上にいろんな立場の人と会話する機会が増えました。以前は「自分が言っても直らない」と思っていましたが、意外と言ってみたら変わるものだし、自分の意見を伝えることは大事だと思いました。先生との立場も近づいた感じがしていて、発言しやすくなったように感じます。
土成)2人は相手を納得させる言葉を言えるようになりましたし、その場を巻き込むきっかけ作りをするようにもなりました。何よりも立場も意見も違う人の考え方を繋いだり、すり合わせたりして、今までになかったみんなが幸せになれる方法を作り上げる力が一番ついたと思いますし、これはルールメイキングの活動でしかつけられなかったと思います。
ーー今後はどのようにルールメイキングに関わりたいですか。
長野)ルールメイキングができる環境にある人を増やしていきたいです。それと同時に、自分たちの学校でもルールを変えたいと思った人が変えられるような環境にしていきたいと思います。校則改正委員会は後輩が活動を引き継いでくれる予定なので、「少しでも疑問に思ったら変えてもよい」という環境になるよう、続けていってほしいです。
笹岡)今、自分たちの学校は発言しやすく、校則を変えやすい環境が整っていると思います。私たちが卒業してからも、この環境が続くよう、後輩に私たちの思いを伝えてから卒業したいと思っています。
土成)本校では具体的な校則から選択の余地がある校則に改正されて半年以上経ったことから、また新しい認識のずれが出てきていることも事実です。そのずれを次世代が解消するムーブメントを起こすためにも、2人から「ルールは変えられる」という勇気づけをしてもらいたいです。加えて「この学校は自分たちでルールを変えて、みんなが幸せになれる学校」という新たな学校文化も作りたいと思っています。

ーーこれからルールメイキングをする人に一言お願いします。
長野)仲間がいると色んな意見を取り入れることができるので、まずは友達や家族の中から、仲間を見つけることが大事だと思います。それから、先生方は違和感があるルールに対しても、なぜそのルールがあるのか私たちが知らない理由を知っていることが多くあります。先生の説明で納得できるのか、できないのかで次の行動が変わってくると思うので、先生方に協力を求めてみることも良いと思います。
笹岡)思っているだけでは何も変わらないと思うので、一度行動してみることが大事だと思います。一回の行動で先生たちの気持ちが変わらなくても、ずっと伝え続けることで、先生たちも「ちょっと話し合ってみようかな」という気持ちになれると思います。具体的には、生徒指導部の先生に直接「校則はこういう点でダメだと思うので、こういう校則にしたらどうですか」と伝えてみてはいかがでしょうか。自分の気持ちを強く持って行動することが大事だと思います。
土成)生徒たちと同じ目線に立ってルールを作るとなると、なし崩しになるのではないかと思って、ルールメイキングに手を付けない先生方もおられると思います。しかし私たち教員が思っている以上に、中学生はよく考え、世の中のことを分かろうとしています。だからこそ、教員自身が思っていることを正直に生徒に話して、すり合わせていく方が健全な関係になれるのではないかと思っています。
新着記事
カタリバではルールメイキングに取り組む
学校・先生・自治体をサポートしています
すでにはじめている学校や自治体、個人の方のお問い合わせもございます。
まずはどのようなサポートが行われているかご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。